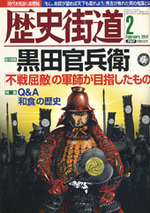雑誌
歴史街道 2014年2月号
今月号の読みどころ
「お手前方の実に天晴れな戦いぶり、われら一同感服してござる。勝ち負けは時の運。ここは将兵の命を無駄にせぬためにも、城を開けて下され」。黒田官兵衛の情理を尽くした説得に、城将は頷き、降伏します。無駄な血を流さず、交渉や調略を用いて敵の戦意を失わせ屈服させる…。豊臣秀吉をして「わしに代わって天下を取る男」と言わしめた、官兵衛の戦法の真骨頂はここにありました。しかしそれは、巧みな弁舌だけでは成し得ません。その根底には、相手を信じる心が不可欠でした。裏切りや保身、謀略が日常茶飯事の乱世に、綺麗事など通用しないことを承知しながら、なぜ官兵衛は困難な道を選んだのか。「天下の軍師」が目指していたものを探ります。第二特集は「Q&A『和食』の歴史」です。
| 公式サイト |  |
|---|---|
| YouTube |
 |
今月号の目次
|
燃える如水 |
黒鉄ヒロシ |
3p |
|
この人に会いたい vol.85 |
岡田准一 |
7p |
総力特集 黒田官兵衛 「不戦屈敵」の軍師が目指したもの
|
総論 戦わずして敵を降す…「天下の軍師」は何を重んじたのか |
小和田哲男 |
14p |
|
ビジュアル1 人を生かす男が、乱世を終わらせた |
20p |
|
|
ビジュアル2 官兵衛を取り巻く人々 |
22p |
|
|
ビジュアル3 山陽道の要衝、黒田氏時代の姫路城推定復元図 |
24p |
|
|
風雅の道より軍学を! 戦乱の播磨で祖父、父より黒田家を託されて |
橋場日月 |
26p |
|
年表・天下平定へと駆けた59年 |
31p |
|
|
近江の佐々木氏か? 播磨の赤松氏か? 黒田氏の出自の謎に迫る |
渡邊大門 |
32p |
|
「一周り大きゅうなられよ」秀吉と半兵衛が示した、才を活かす道 |
秋月達郎 |
34p |
|
[コラム1]秀吉が重用した叔父・休夢 |
39p |
|
|
ビジュアル4 織田か? 毛利か? 激動の播磨 |
40p |
|
|
もう一度、天下のために働きたい…裏切りと幽囚の中で到達した思い |
童門冬二 |
42p |
|
[コラム2] 官兵衛はキリスト教を棄てなかった? |
47p |
|
|
小寺家の家臣か? 織田家の部将か? 官兵衛の主君は誰なのか |
渡邊大門 |
48p |
|
兵は詭道なり! 敵の利点を逆手にとり、不測の危機を好機に転じる |
江宮隆之 |
50p |
|
黒田二十四騎! 官兵衛を支えた勇猛かつ個性豊かな家臣たち |
本山一城 |
56p |
|
これぞ不戦屈敵! 長宗我部、島津、北条らの心を屈して天下平定へ |
工藤章興 |
60p |
|
ビジュアル5 天下統一へ! 稀代の軍師、戦いの軌跡 |
66p |
|
|
現代人が共感できる官兵衛の生き方を描きたい |
中村高志 |
68p |
|
先を読み続けて…それからの官兵衛 |
70p |
|
|
官兵衛と戦国姫路MAP |
74p |
Q&A「和食」の歴史 世界が注目する「日本の美味」の原点とは
|
第1部 料理の変遷 大饗、本膳、懐石…日本人はこんな料理を食べてきた |
熊倉功夫 |
78p |
|
第2部 伝統の味 味噌、醤油、だし…「ほっ」とする味はいつ生まれた? |
熊倉功夫 |
86p |
|
ビジュアル 「うま味」はどこから生まれる? 和食の「だし」の特徴 |
90p |
|
|
|
||
|
巨頭会談の内幕 第1回 籠絡されたルーズベルト |
吉田一彦 |
94p |
|
[連載小説]真田昌幸 連戦記 立国篇 我、六道を懼れず 第9回 |
海道龍一朗 |
100p |
|
「歴史街道」伝言板 |
110p |
|
|
BOOKS・CINEMA |
112p |
|
|
この著者に注目! 村木嵐 |
114p |
|
|
何のために生きるのか? 石田梅岩が語る商売への誇り 現代人が再確認すべき倫理とは |
平田雅彦 |
116p |
|
リスボンからの日帰り旅行 天正遣欧使節も訪れた「森の都シントラ」を満喫する! |
田中次郎 |
122p |
|
明治・大正の古写真に見る 東京・銀座界隈 |
平塚七郎 |
126p |
|
歴史街道脇本陣 |
131p |
|
|
歴史街道・ロマンへの扉 書寫山圓教寺 |
林 宏樹 |
134p |
|
江戸の料理再現づくし 第18回 あさりと大根の鍋・霰豆腐 |
向笠千恵子 料理再現・福田 浩 |
136p |
|
近江花伝 第1回 湖北 神と仏と人と |
写真・文 寿福 滋 |
141p |
歴史街道 とは
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。