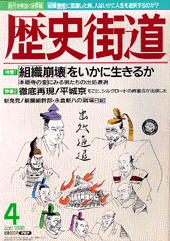雑誌
歴史街道 1998年4月
| 狩野派四〇〇年 4 様式の継承 狩野松栄 |
武田恒夫 高松良幸 |
p143 |
| ちょっと知的に歴史探検 24 MIHO MUSEUM ミホ・ミュージアム 滋賀県甲賀軍信楽町 |
田村淳 |
p141 |
| 文珍の世界史・人物高座 4 クレオパトラ |
桂文珍 |
p138 |
| コメと日本人と伊勢神宮 第56回 ある米屋の「こだわり」と「流通革命」 |
上之郷利昭 |
p132 |
| 特集2 徹底再現! 平城京 そこに、シルクロードの終着点が出現した 朱雀大路の向こうに、一三〇〇年前の都を見つけた |
千田稔 仙頭直美 |
p124 |
| 特集2 徹底再現! 平城京 そこに、シルクロードの終着点が出現した 巨大都市を造りあげた奈良時代人たちの技術力 |
伊藤真人 |
p118 |
| 特集2 徹底再現! 平城京 そこに、シルクロードの終着点が出現した 平城京七四年 |
p116 |
|
| 特集2 徹底再現! 平城京 そこに、シルクロードの終着点が出現した 平城京七四年 |
p116 |
|
| 私の一冊 『十九世紀獨逸哲学思潮』 |
金子光男 |
p112 |
| 「司馬遼太郎」の贈りもの 第七一回 弱者の外交というものは本来成立しがたい 『城塞』二 |
谷沢永一 |
p104 |
| 人間の情景 いま死ぬるなり |
野村敏雄 |
p1998 |
| 専業主婦の、短すぎた歴史 |
落合恵美子 |
p93 |
| 専業主婦の、短すぎた歴史 |
落合恵美子 |
p93 |
| 「バブル崩壊」は繰り返す 世界史のなかの「経済危機」 |
斎藤精一郎 |
p88 |
| 鬼平料理ごよみ 十三 卯月 芹の味噌椀、わけぎと木くらあげの白味噌和え&鱒の味醂漬・嫁菜添え |
逢坂剛 |
p86 |
| 歴史街道・ロマンへの扉 40 土山町 |
岡本紋弥 |
p84 |
| 本木雅弘の歴史初体験 第三回 鬘を付けて、いざ幕末へ! |
本木雅弘 |
p82 |
| 貧乏は、しみじみ味わうものなれど…… 幕臣金欠物語 |
氏家幹人 |
p76 |
| 新発見!新撰組幹部・永倉新八の「戦場日記」 |
多田敏捷 |
p66 |
| 謎に迫る 日本古代史・定説への挑戦 第七回 英雄・ヤマトタケルの本当の姿 |
黒岩重吾 |
p59 |
| 恋さまざま 野茨草紙 その三 焦がれる舎人 |
田辺聖子 |
p56 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 コラム3 今月の「この一言」 その瞬間、武将たちはいかに判断したか? |
p54 |
|
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 コラム2 二四人の武将たちが選んだ道 |
p52 |
|
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 河尻秀隆 「功績」にとらわれた武功派の悲劇 |
堀和久 |
p48 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 松井友閑 専門分野を持つ男の「強み」 |
桐野作人 |
p44 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 女たちの「本能寺」それぞれの戦い |
小石房子 |
p40 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 堀秀政と筒井順慶 一瞬の「迷い」が、その後を決めた |
南原幹雄 |
p36 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 蒲生賢秀 職務に徹した時、道は拓ける |
八尋舜右 |
p32 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 前田利家 「律義さ」で勝ち取った信頼 |
戸部新十郎 |
p28 |
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 コラム1 「本能寺の変」をめぐる基礎知識 |
p26 |
|
| 特集1 「組織崩壊」をいかに生きるか 「本能寺の変」にみる男たちの出処進退 対談 織田家臣団・四人の重臣たちの「明」と「暗」 |
童門冬二 江坂彰 |
p18 |
| にっぽんのたたずまい 12 長崎県長崎市 |
浅井愼平 |
p9 |
| 歴史街道への招待 12 松尾芭蕉 漂泊の人生―滋賀・大津 |
p6 |
歴史街道
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。