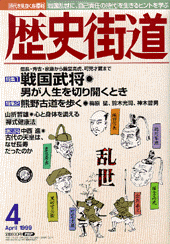雑誌
歴史街道 1999年4月
戦国武将・男が人生を切り開くとき
| 狩野派四〇〇年 16 家法一変 |
武田恒夫 高松良幸 |
p143 |
| 文珍の世界史・人物高座 16 ワシントン |
桂文珍 |
p140 |
| 歴史街道・ロマンへの扉 52 熊野古道 |
鶴田純也 |
p138 |
| 永島敏行の徹底体験 日本人の仕事 歴史は「手」によって作られる アンコール=ワットと木曾の水力発電所 |
永島敏行 |
p132 |
| 特集2 熊野古道を歩く「いのち」がよみがえる道 熊野と日本人の一〇〇〇年 なぜ人々は、この難所を目指したのか |
神木哲男 |
p126 |
| 特集2 熊野古道を歩く「いのち」がよみがえる道 「奥駈け」が僕にくれたもの |
鈴木光司 |
p124 |
| 特集2 熊野古道を歩く「いのち」がよみがえる道 今こそ、「母なる熊野」に帰れ |
梅原猛 |
p120 |
| 私の一冊 『神々の指紋』 |
加藤一良 |
p110 |
| 「司馬遼太郎」の贈りもの 第八三回 「非合理なエネルギー」が大変革を生み出す 『花神』三 |
谷沢永一 |
p104 |
| あかんべえ 十二 深川ふね屋不思議ばなし |
宮部みゆき |
p96 |
| 白隠禅師に学ぶ 心と身体を調える「禅式健康法」 |
山折哲雄 |
p91 |
| 鬼平料理ごよみ 二三 卯月 蛤と豆腐と葱の 小鍋立て |
北原亞以子 |
p88 |
| 特別企画 多久聖廟 「温故知新」から「温故創新」へ これからの人づくり、町づくり |
横尾俊彦 |
p86 |
| 特別企画 多久聖廟 多久に「孔子」を訪ねる |
p84 |
|
| 特別企画 多久聖廟 かくして、孔子の教えは、人々に浸透していった |
北条良平 |
p77 |
| 戦国道具図鑑10 能面・狂言面 |
本山賢司 |
p72 |
| 花のお江戸のトイレ物語 |
吉原健一郎 |
p67 |
| 謎に迫る 古代の天皇は、なぜ長寿だったのか |
中西進 |
p60 |
| 恋さまざま野茨草紙 その十五 霧立ちわたる |
田辺聖子 |
p54 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 徹底分析 戦国乱世の評価基準2 評価される六つのポイント |
小和田哲男 |
p48 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 可児才蔵 主を選ぶのは自分自身 |
八尋舜右 |
p44 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 黒田官兵衛 「大失敗」で開けた新しい人生 |
江坂彰 |
p40 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 福島正則の家臣たち 突然の改易、その時いかなる選択をしたのか |
桐野作人 |
p36 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 徹底分析 戦国乱世の評価基準1 戦国時代の抜擢・採用・リストラ |
小和田哲男 |
p30 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 藤堂高虎 生き方を変えた「捨て身の大芝居」 |
神坂次郎 |
p26 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 金井善立 初心でのぞんだ「七十歳の初陣」 |
野村敏雄 |
p22 |
| 特集 戦国武将 男が人生を切り開くとき 信長 秀吉 家康 三人の天下人は、こうして人生を切り開いていった |
上之郷利昭 |
p16 |
| にっぽんのたたずまい 24 東京・下北沢 |
浅井愼平 |
p9 |
| 歴史街道への招待 24 本居宣長 商人から学者へ――三重・松坂 |
p6 |
歴史街道
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。