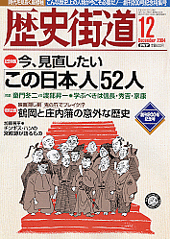雑誌
歴史街道 2004年12月
今、見直したい「この日本人」52人
| 画像をクリックすると、拡大した見本ページの画像を閲覧することができます |
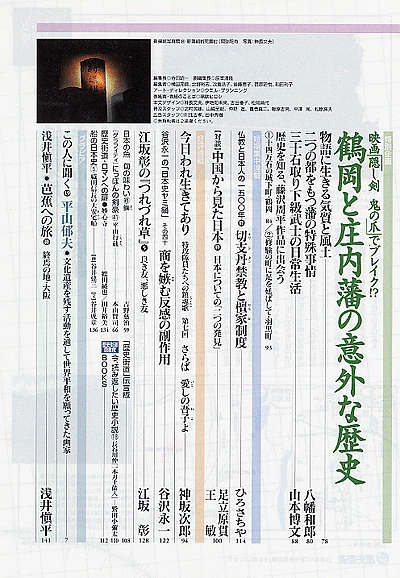
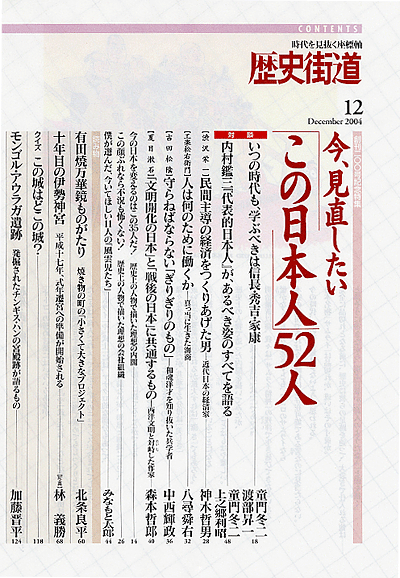
|
| 表紙のことば 起死・武士度 |
黒鉄ヒロシ |
p3 |
| この人に聞く 19 |
平山郁夫 |
p7 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 今の日本を変えるのはこの35人だ! 歴史上の人物で描いた理想の内閣 |
童門冬二 |
p14 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 対談 いつの時代も、学ぶべきは信長・秀吉・家康 |
童門冬二 渡部昇一 |
p18 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 この顔ぶれなら不況も怖くない! 歴史上の人物で描いた理想の会社組織 |
童門冬二 |
p26 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 渋沢栄一 民間主導の経済をつくりあげた男 近代日本の経済家 |
神木哲男 |
p28 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 工楽松右衛門 人は何のために働くか 真っ当に生きた海商 |
八尋舜右 |
p32 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 吉田松陰 守らねばならない「ぎりぎりのもの」 和魂洋才を知り抜いた兵学者 |
中西輝政 |
p36 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 夏目漱石 「文明開化の日本」と「戦後の日本」に共通するもの 西洋文明と対峙した作家 |
森本哲郎 |
p40 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 僕が選んだ、今いてほしい11人の「風雲児たち」 |
みなもと太郎 |
p44 |
| 創刊二〇〇号記念特集 今、見直したい「この日本人」52人 対談 内村鑑三『代表的日本人』が、あるべき姿のすべてを語る |
童門冬二 上之郷利昭 |
p48 |
| 日本の魚 旬の味わい 最終回 鰤 |
吉野慈治 |
p58 |
| 焼き物の町の「小さくて大きなプロジェクト」有田焼万華鏡ものがたり |
北条良平 |
p60 |
| にっぽんの剣豪 41 平山行蔵 |
本山賢司 |
p66 |
| 十年目の伊勢神宮 平成十七年、式年遷宮への準備が開始される |
p68 |
|
| 特別企画 映画「隠し剣 鬼の爪」でブレイク!? 鶴岡と庄内藩の意外な歴史 物語に生きる気質と風土 |
p78 |
|
| 特別企画 映画「隠し剣 鬼の爪」でブレイク!? 鶴岡と庄内藩の意外な歴史 二つの都をもつ藩の特殊事情 |
八幡和郎 |
p80 |
| 特別企画 映画「隠し剣 鬼の爪」でブレイク!? 鶴岡と庄内藩の意外な歴史 歴史を知る、藤沢周平作品に出会う 十四万石の城下町・鶴岡 |
p84 |
|
| 特別企画 映画「隠し剣 鬼の爪」でブレイク!? 鶴岡と庄内藩の意外な歴史 三十石取り下級武士の日常生活 |
山本博文 |
p88 |
| 特別企画 映画「隠し剣 鬼の爪」でブレイク!? 鶴岡と庄内藩の意外な歴史 歴史を知る、藤沢周平作品に出会う 修験の町に足を延ばして・羽黒町 |
p93 |
|
| 今日われ生きてあり 特攻隊員たちへの鎮魂歌 第七回 さらば 愛しの吾子よ |
神坂次郎 |
p94 |
| 短期集中連載 対談 中国から見た日本 最終回 日本についての「二つの発見」 |
足立原貫 王敏 |
p100 |
| 歴史街道図書館 今、読み返したい歴史小説 Vol18『一本刀土俵入』長谷川伸著 |
鷲田小彌太 |
p110 |
| 短期集中連載 仏教と日本人の一五〇〇年 最終回 切支丹禁教と檀家制度 |
ひろさちや |
p114 |
| 歴史街道スペシャル「名城を歩く」シリーズ完結記念 クイズ この城はどこの城? |
p118 |
|
| 谷沢永一の日本史ヤミ鍋 四十 商を嫉む反感の副作用 |
谷沢永一 |
p122 |
| モンゴル・アウラガ遺跡 発掘されたチンギス・ハンの宮殿跡が語るもの |
加藤晋平 |
p124 |
| 江坂彰の『つれづれ草』 5 良き友、悪しき友 |
江坂彰 |
p128 |
| 歴史街道・ロマンへの扉 119 妙心寺 |
鶴田純也 |
p134 |
| 船の日本史 第5回 織田信長の大安宅船 |
谷井成章 |
p136 |
| 芭蕉への旅 最終回 終焉の地・大阪 |
浅井愼平 |
p141 |
歴史街道
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。