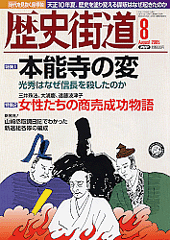雑誌
歴史街道 2005年8月
本能寺の変・光秀はなぜ信長を殺したのか
| 画像をクリックすると、拡大した見本ページの画像を閲覧することができます |
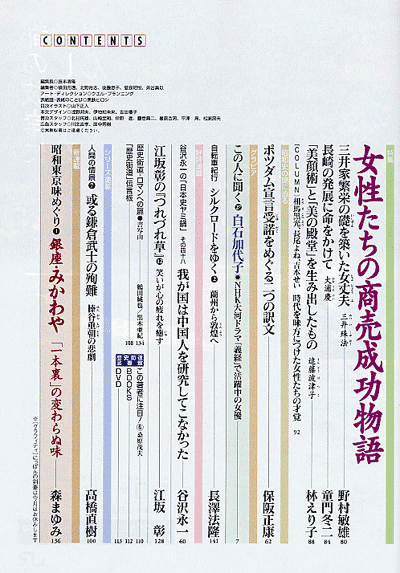
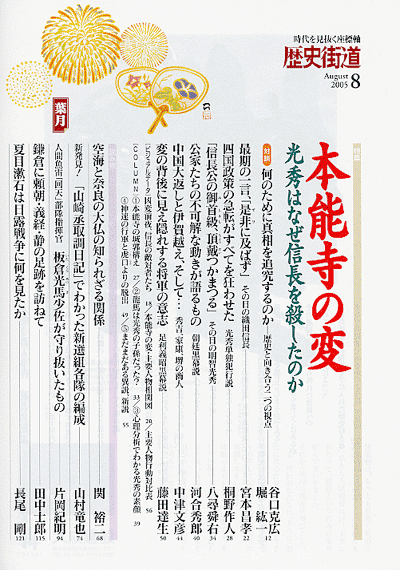
|
| 表紙のことば 本能寺殺人事件 読者共犯説 |
黒鉄ヒロシ |
p3 |
| この人に聞く |
白石加代子 |
p7 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 対談 何のために真相を追究するのか 歴史と向き合う二つの視点 |
谷口克広・堀紘一 |
p12 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか ビジュアルデータ1 凶変前夜、信長の敵対者たち |
p18 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか ビジュアルデータ2 本能寺の変・主要人物相関図 |
p20 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 最期の一言、「是非に及ばず」 その日の織田信長 |
宮本昌孝 |
p22 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか コラム1 本能寺の城郭構え |
p27 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 四国政策の急転がすべてを狂わせた 光秀単独犯行説 |
桐野作人 |
p28 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか コラム2 龍馬は光秀の子孫だった? |
p33 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 「信長公の御首級、頂戴つかまつる」 その日の明智光秀 |
八尋舜右 |
p34 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか コラム3 心理分析でわかる光秀の素顔 |
内藤誼人 |
p39 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 公家たちの不可解な動きが語るもの 朝廷黒幕説 |
河合秀郎 |
p40 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 中国大返しと伊賀越え、そして・・・ 秀吉、家康、堺の商人 |
中津文彦 |
p44 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか コラム4 神速の行軍と虎口よりの脱出 |
p49 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 変の背後に見え隠れする将軍の意志 足利義昭黒幕説 |
藤田達生 |
p50 |
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか コラム5 まだまだある異説、新説 |
p55 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか ビジュアルデータ3 主要人物行動対比表 |
p56 |
|
| 特集 本能寺の変 光秀はなぜ信長を殺したのか 知るための本 |
p58 |
|
| 谷沢永一の日本史ヤミ鍋 四八 我が国は中国人を研究してこなかった |
谷沢永一 |
p60 |
| 昭和史の謎に迫る 第5回 ポツダム宣言受諾をめぐる二つの訳文 |
保阪正康 |
p62 |
| 空海と奈良の大仏の知られざる関係 |
関裕二 |
p68 |
| 新発見!「山崎丞取調日記」でわかった新選組各隊の編成 |
山村竜也 |
p74 |
| 特集 女性たちの商売成功物語 三井家繁栄の礎を築いた女丈夫 三井殊法 |
野村敏雄 |
p80 |
| 特集 女性たちの商売成功物語 長崎の発展に命をかけて 大浦慶 |
童門冬二 |
p84 |
| 特集 女性たちの商売成功物語 「美顔術」と「美の殿堂」を生み出したもの 遠藤波津子 |
林えり子 |
p88 |
| 特集 女性たちの商売成功物語 コラム 相馬黒光、長尾よね、吉本せい 時代を味方につけた女性たちの才覚 |
藤谷恵 |
p92 |
| 人間魚雷「回天」部隊指揮官 板倉光馬少佐が守り抜いたもの |
片岡紀明 |
p94 |
| 人間の情景 第7回 或る鎌倉武士の殉難 榛谷重朝の悲劇 |
高橋直樹 |
p100 |
| この著者に注目! vol6 |
p110 |
|
| DVD 『笑いの大学』 |
p113 |
|
| 鎌倉に頼朝・義経・静の足跡を訪ねて |
田中士郎 |
p115 |
| 夏目漱石は日露戦争に何を見たか |
長尾剛 |
p121 |
| 江坂彰の『つれづれ草』 12 笑いが心の疲れを癒す |
江坂彰 |
p128 |
| 歴史街道・ロマンへの扉 127 書写山 |
鶴田純也 |
p134 |
| 昭和東京味めぐり 第1回 銀座・みかわや 「一本裏」の変わらぬ味 |
森まゆみ |
p136 |
| 自転車紀行 シルクロードをゆく 2 蘭州から敦煌へ |
長澤法隆 |
p141 |
歴史街道
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。