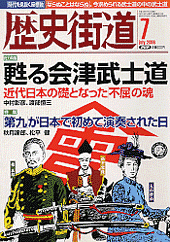雑誌
歴史街道 2006年7月
甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂
| 画像をクリックすると、拡大した見本ページの画像を閲覧することができます |

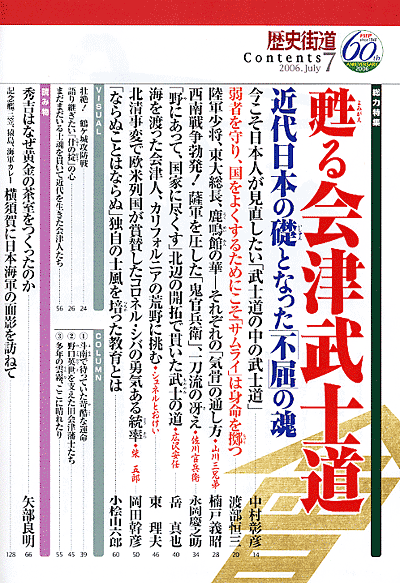
|
| 表紙のことば 会津はV |
黒鉄ヒロシ |
p3 |
| この人に聞く 38 |
田中美里 |
p7 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 今こそ日本人が見直したい「武士道の中の武士道」 |
中村彰彦 |
p14 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 弱点を守り、国をよくするためにこそ「サムライ」は身命を擲つ |
渡部恒三 |
p20 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 ビジュアルデータ 壮絶!鶴ケ城攻防戦 |
p24 |
|
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 語り継ぎたい「什の掟」の心 |
p26 |
|
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 陸軍少将、東大総長、鹿鳴館の華―それぞれの「気骨」の通し方 山川三兄弟 |
楠戸義昭 |
p28 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 西南戦争勃発!陸軍を圧した「鬼官兵衛」、一刀流の冴え 佐川官兵衛 |
永岡慶之助 |
p34 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 コラム1 斗南で待っていた過酷な運命 |
p39 |
|
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 「野にあって、国家に尽くす」北辺の開拓で貫いた武士の道 広沢安任 |
岳真也 |
p40 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 コラム2 野口英世を支えた旧会津藩士たち |
小桧山六郎 |
p45 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 海を渡った会津人、カリフォルニアの荒野に挑む シュネルとおけい |
東理夫 |
p46 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 北清事変で欧米列国が賞賛したコロネル・シバの勇気ある統率 柴五郎 |
岡田幹彦 |
p50 |
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 コラム3 多年の雲霧、ここに晴れたり |
p55 |
|
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 まだまだいる士魂を貫いて近代を生きた会津人たち |
p56 |
|
| 総力特集 甦る会津武士道 近代日本の礎となった「不屈」の魂 「ならぬことはならぬ」独自の士風を培った教育とは |
小桧山六郎 |
p60 |
| 谷沢永一の日本史ヤミ鍋 五九 又たも負けたか八聯隊 |
谷沢永一 |
p64 |
| 秀吉はなぜ黄金の茶室をつくったのか 茶の湯をめぐる六つの謎 |
矢部良明 |
p66 |
| にっぽんの剣豪 58 松崎浪四郎 |
本山賢司 |
p74 |
| 特集 「第九」が日本で初めて演奏された日 ベートーベンの世紀 前編 戦争がもたらした「平和と自由への賛歌」 |
秋月達郎 |
p78 |
| 特集 「第九」が日本で初めて演奏された日 敗者の痛みを知る男・松江豊寿を演じて |
松平健 |
p82 |
| 特集 「第九」が日本で初めて演奏された日 板東俘虜収容所の全容 |
p86 |
|
| 特集 「第九」が日本で初めて演奏された日 ベートーベンの世紀 後編 今も受け継がれる「第九」のこころ |
秋月達郎 |
p88 |
| 特集 「第九」が日本で初めて演奏された日 コラム 墓碑から復活した日独の絆 |
p92 |
|
| 陰陽五行が語る三人の天下人 第二回 信長はなぜ「盆山」を重んじたのか |
吉野裕子 |
p94 |
| 小説 利休にたずねよ 第一回 死を賜る |
山本兼一 |
p100 |
| BOOKS・DVD ブレイブハート |
p112 |
|
| 図解 太平洋戦争入門 データと地図で甦る戦いの全貌 最終回 ポツダム宣言受諾!3年8カ月にわたる戦いは終わった |
三野正洋 |
p115 |
| 山本博文教授の江戸学講座 最終回 明暦の大火、そのとき江戸は・・・百万都市を襲った災害と対策 後編 |
逢坂剛・宮部みゆき・山本博文 |
p122 |
| 記念艦三笠、猿島、海軍カレー 横須賀に日本海軍の面影を訪ねて |
p128 |
|
| 歴史街道・ロマンへの扉 138 伊勢 |
鶴田純也 |
p134 |
| 昭和東京味めぐり 第12回 高田の馬場 文流 海の幸たっぷりのスパゲッティ |
森まゆみ |
p136 |
| 写真紀行 スイス・歴史の交差点 第三回 氷河期が形見に残した可憐な高山植物たち |
中塚裕・鈴木光子 |
p141 |
歴史街道
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。