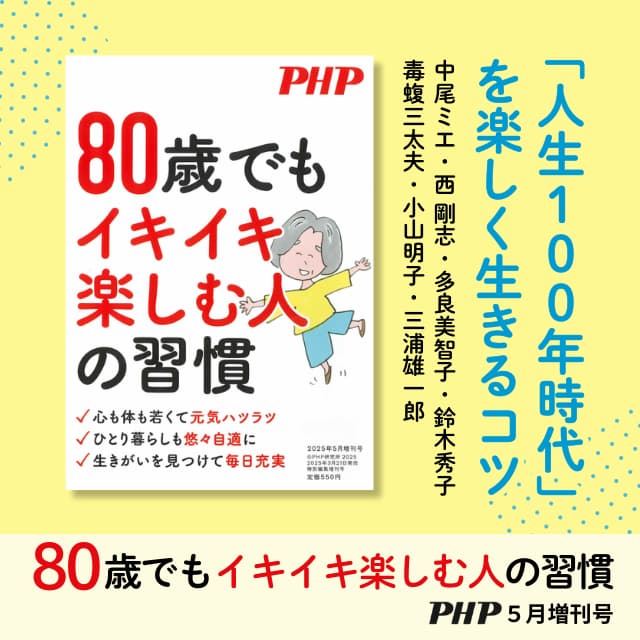第54回PHP賞受賞
所属しているコーラスグループの発表会があり、私は夫や兄、友人たちを招待した。
ちょうどそのころ、夫は白内障の悪化で両目の視力が弱くなっていた。そのこともあり、夫は車を運転できない。会場へはタクシーで来てもらうことにした。
問題は、会場へ着いた後だった。階段の多い場内を、一人で歩かせるわけにはいかない。
「いい? 会場へ着いたら、私の携帯へ電話をするのよ。コールは2回。そうしたら入り口まで迎えに行くから待っていてね」
視力は急に悪くなるわけではない。少しずつ見えなくなっていく。夫のことだから、どのくらい見えないのかわかりそうなものだが、夫といえども別の人間。見えないことの不便さは、なかなか想像できなかった。
愛があるから、ついてきた
夫は、日常生活でも、常に補助を必要とした。
通院の送り迎えは私の役目だ。理髪店一つ行くにも同様。その煩雑さに閉口した。
食事のときは、テーブルの上にあるおかずが見えないようだった。
「はい、これはトマト。こっちは刺身。向こうには漬物があるわ」
そう教えても、ものの形がはっきり見えないので箸でつかめない。仕方がないので、口元までもっていく。
お風呂も一人では入れない。転んで怪我をしてしまわないよう、私も一緒に入った。
寒い冬は、湯船に浸かる夫を横目に、ガタガタ震えながら温まるのを待った。
夫との生活は「忍耐」と「優しさ」が不可欠だった。どんなに大変でも怒るまいと思った。でもそれは、視力が弱くなったからではない。
恋人のときは明るくて行動的で、前向きな性格が好ましかった。
だが、結婚生活には、それらの性格が少なからず災いした。
夫は「相談」というものをしない人だった。
どんなに大事なことでも一人で決めてしまう。
あとさき考えずに目の前の誘惑に惹かれ、飛びこんでしまう。
その繰り返しに私は振り回まわされた。しかし、ついていくしか選択肢はなかった。いや、夫が私を愛してくれているという確信があったからこそ、離れなかった。
結婚をして40年あまり、決して平たんな道ではなかった。
人には言えない苦しみを味わった。死んだほうが楽だと思ったこともある。
お互いに仕事を引退し、年老いてくると、今まで反目したことなど、もうどうでもよくなる。ましてや、病を抱えている夫が私の手にすがってくれば、愛おしさも募ってくる。
入り口に迎えに行き、手を繋いで会場内を歩いていると、夫が、「仲良しこよしだね、こんな年寄り夫婦が手を繋ぐなんて。笑われちゃうね」
と苦笑いをしたが、繋いだ手を自分から離そうとはしなかった。
友人から聞いた夫の言葉
発表会が終了し、先に帰る夫のためにタクシーを頼もうとしていると、友人の貴美子さんが、夫を乗せると申し出てくれた。
その夜、お礼を言うために彼女に電話をかけた。しばらく発表の感想などを話していた彼女が、「旦那さん、何か言ってなかった?」と、含みをもたせた言い方をした。「何も」と言うと、帰りの車中でのことを話してくれた。
貴美子さんは雑談のなかで、私のことを、
「本当に明るくて面白い人ですね」
と褒めてくれたそうだ。
夫はそれには答えず、
「我慢強いやつですから……」
と、一言だけ言ったという。
「私ねえ、いろいろな人から奥さんを褒める言葉を聞いたことがあるけれど、中村さんの旦那さんの言葉は、すごく胸に響ひびいたの」
貴美子さんは感動したように言葉に力を入れる。
「そう、そんなこと言ったの」
後部座席で、見えない目を窓の外に泳がせながらつぶやく夫の顔を思い浮う かべた。
「こんな素敵な賛辞の言葉は、絶対に教えてあげなくちゃ、と思ったのよ」
携帯をテーブルに置いてからしばらく、私はそこに佇ずんでいた。そのうちに、目が潤んできた。「我慢強い」という言葉が夫から出るとは思わなかった。
それを素敵と受けとめ教えてくれた、貴美子さんの優しい心にも感謝した。
階下におりると、夫が疲れたようにソファーに横になっていた。静かな寝息が聞こえてくる。何も言うまいと思った。口に出すと、たいせつな夫の言葉が色あせたものになってしまう。このまま胸にしまって、夫と生きていこうと思った。
中村実千代(栃木県小山市・無職・62歳)