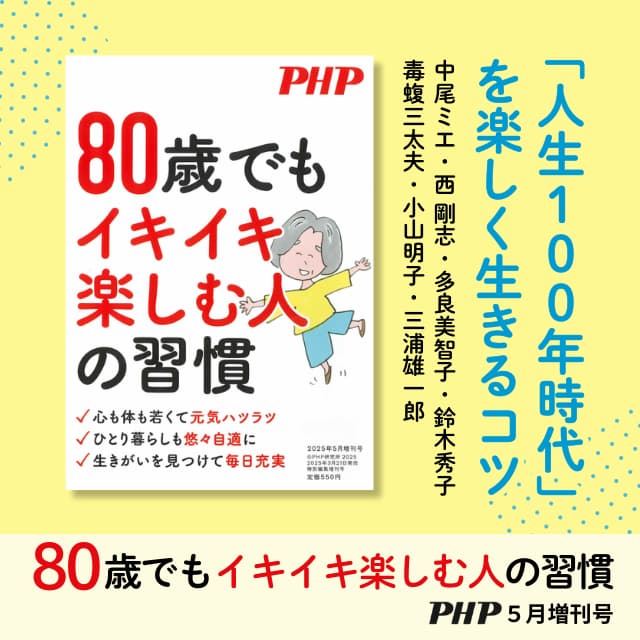第55回PHP賞受賞作
稲田知明(兵庫県尼崎市・会社員・23歳)
小学生のとき、何度も転校をした。お別れ会があるたびに悲しくて仕方がなかった。転校を繰り返すうちに、新しい人間関係を作るのが怖くなり、家に閉じこもるようになった。
父が東京で家を買い、引越すことがなくなってからも、中学も、高校も、長くても3年で別れが来る。どうせいつか別れてしまうなら、もう友達なんていらない。
私は通信制の高校を選び、大学でも人との関係には距離をとった。とにかく、いつ別れてもいいように、いつ関係が切れても後悔しないために、誰にでも優しく、誰にでも平等に、笑顔を振りまいて過ごしていた。
それは、誰との関係がいつ切れても、変わらぬ日常が流れていくようにするための最大の自己防衛だった。
「一緒に働きませんか?」
大学1年生のとき、外部講師の1人として、Yさんという女性がやってきた。とある出版社で編集長をしていたYさんは、私たち大学生を前にして、出版社でYさん自身がどのように働いているのかを語っていた。
授業が終わった後、私はいつものように、挨拶と、記憶に残らないような会話をし、なんとなく名刺交換をして、Yさんと別れた。
数カ月後、Yさんから私にメールが届いた。
「会社を立ち上げることになりました。一緒に働きませんか?」
当時大学2年生だった私は、ちょうどインターンシップ先を探していたこともあり、Yさんの誘いに乗って、新しく立ち上がった小さな出版社で働くことにした。期間は半年間。
最初は出版記念パーティーの運営スタッフから始まり、出版社に入ったはずなのに、任されるのは企画の運営やスタッフばかりだった。瞬く間に半年が過ぎ去った頃、Yさんが私に言った。
「このままここでアルバイトしない?」
働くうちに、インタビューの同席や原稿の確認など、出版社らしい業務をいくつか任せてもらえるようになった。そして自分の名前が本の奥付に印刷されたときは、嬉しくて飛び上がりそうになった。自分の名前が刻まれた本が書店に並んだところを見にいった。イベントで手売りして、何冊も本を売った。本ができるまでの工程を知っているからこそ、届けたい、伝えたい、という想いがこもった。
「さようなら」で終わらない
気が付くと、出版社でのアルバイトもいつの間にか2年を超えていた。
4年生になり、細々と行なっていた就職活動を終えたとき、ふと、Yさんの顔が浮かんだ。
ずいぶん夢中になっていたけれど、また、別れの季節がやってきたのだ。
「Yさん、就職が決まりました」
Yさんは、にっこり笑ってから、泣いて喜んでくれた。就職先は兵庫県。東京からずいぶん遠くに離はなれてしまう。
「送別会しないとね」
またお別れだ。私は、いつもこの瞬間が嫌いだった。どんな顔をすればいいのかわからなくなってしまう。Yさんは、両手いっぱいの花束を持ってきて「おめでとう」と私に差し出し、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、2年間の想いを込めて手紙を読んでくれた。
手紙の最後でYさんは言った。
「あなたはこれから、たくさんの人に『ありがとう』と言われることになるでしょう。そして、それと同じくらい他の人に対して『ありがとう』と口にするのだと思います。あなたの未来に、たくさんのありがとうがあふれることを、私はもう、よくわかっています」
Yさんと出会ってからの2年間、私はたくさんの失敗をしてきた。でも、それ以上に、たくさんの人から感謝されていたことをYさんはずっと見ていた。
「だからこそ、今日は言わせてください。出会ってくれて、ありがとう」
Yさんはグッと強く目を閉じ、涙がこぼれた。私はそれをじっと目に焼き付けた。
もしも、この出会いが無かったら、Yさんが、こんなに私のことを大切にしてくれていなかったら、私は兵庫県へ旅立つことができただろうか。
Yさんと離れるのは、辛くて、苦しかった。
でも、そこに一片も後悔の念がないのは、今日離れてもいいと、浅く付き合っていたからではない。2年という歳月の中でYさんは、私が人との間に作っていた壁を壊してくれた。最後の日、ボロボロと泣き出すYさんを目の前にして、ようやくそれに気が付いたのである。
別れとは「さようなら」だと思っていた。
しかし、私に掛けられた言葉は無数の「いってらっしゃい」だった。力強い応援に送り出されて、私は兵庫県へ旅立つ。
「いってきます」
Yさんからの手紙をコートの内ポケットに入れると、私は飛行機へ乗り込んだ。