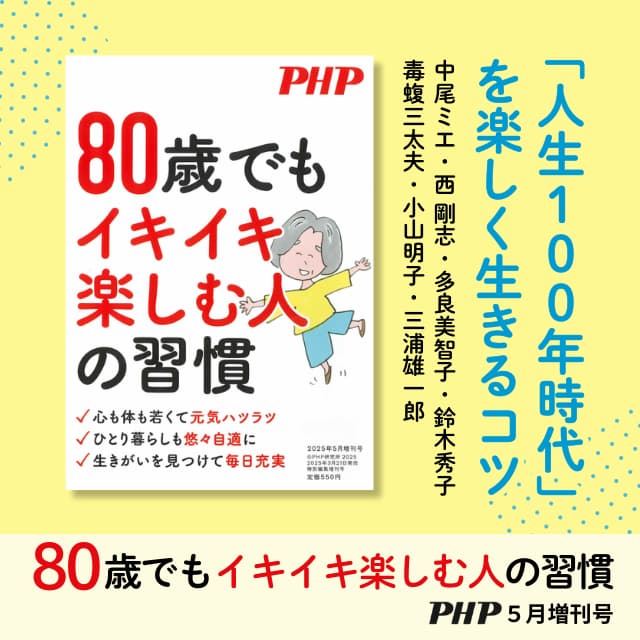第57回PHP賞受賞作
佐々木瞳
岐阜県羽島郡・介護福祉士・二十二歳
あの日、私は、慣れないスーツを着て就職活動をしていた。歩き疲れ、靴擦れを起こしたかかとに、十二月の冷たい風が刺さる。夕日も沈み、あたりはすっかり暗くなっていた。
帰りのバス停に向かって歩いていると、交差点に差しかかった。街は仕事帰りのサラリーマンや、冬休みを満喫している学生たちで溢れ、イルミネーションが点灯し始めていた。
信号機が青になると、前から後ろからと、人の波が押し寄せてくる。足がズキズキと痛み、歩く人のペースに合わせられない私は、人ごみに押されるように端へと寄っていった。
交差点を渡り、改装したばかりのファミリーレストランの前を通るとき、白髪の男性の後ろ姿が目に入った。男性は壁に身体をつけ、足を地面に滑らせるように、ゆっくりゆっくり歩いていた。男性の足元に杖が落ちていることに気づき、思わず私は立ち止まった。
男性が視覚障がい者だと、すぐに分かった。早くあの杖を拾ってあげなくては。そう思った矢先、誰かが「あの人、何かヤバくない?」と男性に向かって言った。心ない言葉が耳に入った途端、臆病になる。結局、私は杖を拾うこともできず、その場を通り過ぎた。
また交差点に差しかかる。歩行者信号が青になり、信号機からは鳥の鳴き声が響いた。音声付き信号機は、視覚障がい者を誘導するために作られた、と学生時代のボランティアで学んだことを思い出した。
同時に、あの人ごみを視覚障がい者が歩行する危険や恐怖を考えると、自分はなんて最低なことをしたんだ、と思った。
バス停に着いてからも、「誰かが気づいてくれるはず」と心の中で何度も唱えた。
けれど、後悔は大きくなるばかりだ。
いつの間にか、かかとの痛みも忘れ、私は男性のいたファミリーレストランへと走りだした。このままバスに乗れば後悔し、立ち直れなくなる。そんな気がしていた。
一歩の慎重さに気づけなかった
たどり着くと、男性はまだ誰にも気づいてもらえず、ゆっくり歩を進めていた。
「大丈夫ですか」
私は落ちていた杖を拾い、男性に声をかけた。背中に人の視線を感じる。悪いことをしている訳ではないのに、恥ずかしくなった。
杖を手に渡すと男性は肩をビクッと動かし、驚いた様子だったが、「ありがとうございます。探していました」と言い、私に深くお辞儀をしてくださった。目の焦点は合っていなかったが、気持ちが伝わってくる表情だった。
駅まで行くつもりだという男性を、このまま一人で行かせるわけにはいかないと思い、一緒に歩くことにした。
私が男性の右手を握り、二人で歩いていく。また周囲の視線を強く感じた。緊張と、注目される恥ずかしさが、再び私を臆病にさせる。
下を向き、夢中で歩いていたので、男性とは一言も会話をしなかった。
エスカレーターに乗るとき、男性の握った手から、痛いと感じるほどに強い力が伝わってきた。けれど、男性は何も言わず私の隣をついてきた。
だが、エスカレーターを降りるときに男性がバランスを崩し、初めて気がついた。私は歩く速さも一人のときと変えず、少しの段差があっても声をかけなかったのだ。視覚障がい者の男性にとっては、一歩がどれだけ慎重なものか。自分のことでいっぱいになっていて、男性のことを気にかける余裕がなかった。
「ごめんなさい! すみません、私……」と何度も謝る私に、男性は、「いえいえ。ありがとうね、嫌な思いさせてごめんね」と言った。
駅員さんは男性のことを知っている様子だった。握っていた手が解放されると、温かさとしびれを感じた。駅員さんに「エラいね」と言われても、男性に「ありがとう」と言われても、罪悪感しかなかった。
見えない気持ちを見つける
帰りのバスの中で、私はたくさん泣いた。自分の行動すべてが悔しくて、まだ温かい左手を見ると、男性が強く握ったあの感覚を思い出した。私の手だけを頼りにしていた男性に怖い思いをさせてしまったこと、それでも手を離さないように強く握っていた男性を思うと心が痛かった。
私は今、介護福祉士として特別養護老人ホームで働いている。技術だけではなく、常に人の気持ちに寄り添うことが求められる。相手の目や耳、口、身体から、見えない気持ちを見つけることの難しさを日々感じる。
そのたびに立ち止まり、あの男性を思い浮かべる。苦い思い出が、いつも私に頑張れと勇気をくれる。あの日、あの男性に出会えたことで、今の私があるのだと思う。いつかあの男性に、もう一度会いたいと願っている。