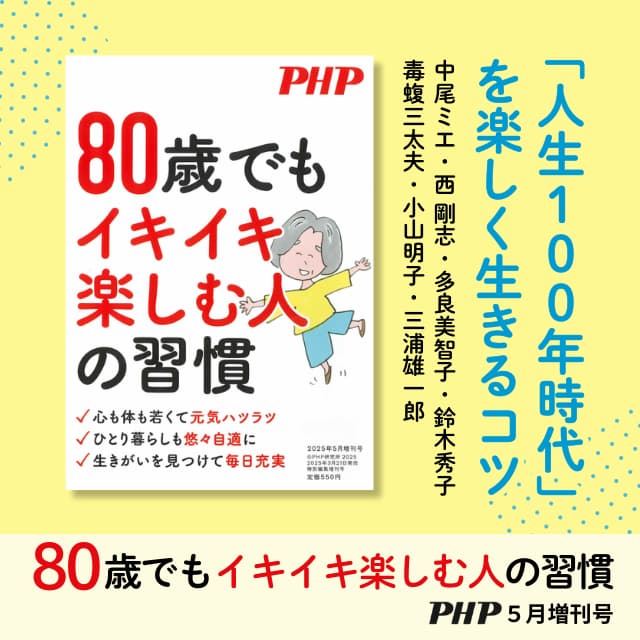第58回PHP賞受賞作
感王寺美智子
福岡県朝倉市・自営業・五十八歳
乳がんになった。
手術後、抗がん剤治療が始まった。
ある日、指で髪をすくと、ゴソッと束のまま抜けた。そして、あっという間にツルツルの頭になった。太い眉も、自慢だった長いまつ毛もなくなった。
用意していたウィッグをかぶってみたが、どうも馴染まない。青白いマネキンのようだ。
気丈に治療を続けてきたが、鏡の中の自分を見たときに、はじめて涙が出てきた。濡らすまつ毛もなく、涙の粒はコロコロと玉のまま頬を転がり落ちた。
もう、どこにも出かけたくないと思った。
「帽子にすればいいんじゃない? 髪がないから、かえっていろんな帽子を楽しめると思うわ」
編み物好きの母が言った。
なるほど。不自然と感じるウィッグをかぶって人目を気にするより、帽子なら自然だし、おしゃれも楽しめるかもしれない。
きっと母が素敵な帽子を編んでくれるのだろう。私はそう期待していた。
しかし、数日たっても母は帽子を編みはじめる様子がない。
「ねえ、帽子は?」
待ちきれず問うと、母は押し入れからたくさんの毛糸が入った箱を出してきて、ガサッと私の前に置いた。
「何を言ってるの? 自分で編むのよ」
「え?」
編み棒など、持ったこともない。
それに、抗がん剤の副作用で指先がしびれている。無理だ。
「人の体は元に戻ろうとして、がんばるのよ。自分の力を信じて」
母は毛糸の玉を、私の手に握らせた。
がんばる体を、ちゃんと愛そう
その日から、母に習いながら編み物をはじめた。まずはシンプルなニット帽を一緒に編むことにした。しかし、感覚のない指から、何度も編み棒が滑り落ちる。イラつき、ため息が出た。
「あなたの指は、今、一所懸命がんばっているのよ」
母は私に合わせて、ゆっくりと編み棒を進めていた。
私は、自分の手のひらをじっと見た。
指先がすまなそうに、小刻みに震えている。
自分の指に、じんわりと愛おしさがこみあげてきて、目頭が熱くなった。
「ごめん。一緒にがんばろうね」
私は指に話しかけ、きゅっと手のひらを握った。そして、再び編み棒をとる。
がんばる自分の体を、ちゃんと愛してあげなきゃ。そう思った。
十日後、母とおそろいのニット帽ができあがった。うれしくて、さっそく二人でかぶり、街へ出かけた。
青空色のニット帽に、白い雪がハラハラと舞い落ちる。母と二人、女学生に戻ったような気持ちになり、そっと手をつないだ。
カフェに入り、帽子をかぶったまま向き合い、紅茶を飲んだ。
「似合っているよ」
「母さんも」
笑いながら、そういえば、髪を失ってから街へ出たのははじめてだった、と気づいた。
「自分の力を信じて」編む
それから、母といくつも帽子を編んだ。レゲエミュージシャンがかぶるような帽子、パリジェンヌみたいなベレー帽。ちょっとずつだが上達し、リボンを編みこんだ帽子や、猫耳がついた帽子にもチャレンジした。
「その帽子、ステキ!」
尻込みしていた友人たちとの集まりにも、出かけるようになった。友人たちはみな、私の帽子をほめてくれた。
「感王寺さんの帽子、いつも楽しみです。治療室がパッと明るくなるんですよ」
看護師さんが言ってくれた。
そして、私と同じ髪を失った患者さんたちの要望で、母に先生となってもらい、編み物教室を開いた。編むことは、患者さんの楽しみだけでなく、リハビリにもなった。
あの日「自分の力を信じて」といった母の言葉の意味がやっとわかった。
抗がん剤治療を終えたころ、東日本大震災が起きた。ウィッグや帽子も津波に流され、周りの人の目を気にしながら避難所生活を送っている、という被災地の患者さんの声が聞こえてきた。
編み物教室で一緒に帽子を編んだ患者さんたちに連絡を取った。みんな、同じ思いを抱いていた。
あっという間に段ボールいっぱいの帽子が集まった。それはまさしく、みんなが「自分の力を信じて」編んだ帽子たちだ。