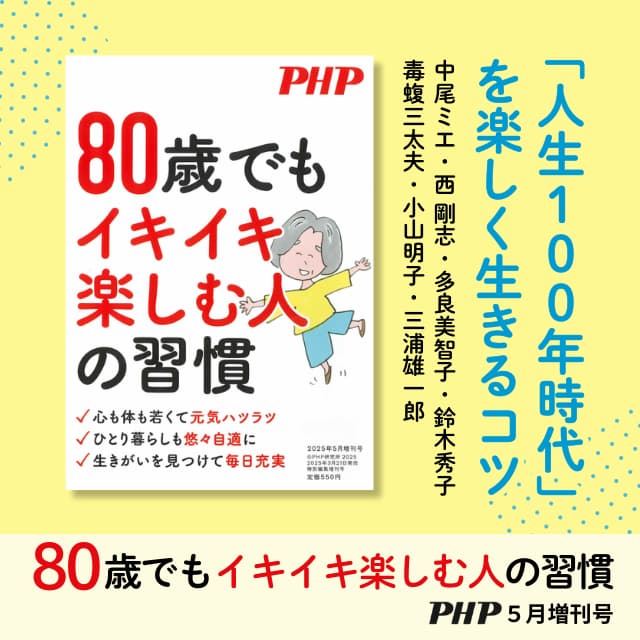第59回PHP賞受賞作
白幡妙子
山形県鶴岡市・無職・六十歳
平成五年の春、娘が生まれた。
はじめての子で不安もあったが、私はこれから始まる幸せな生活を楽しみにしていた。
生後三日目の朝、先生に呼ばれ、娘にダウン症の疑いがあると告げられた。
一気に絶望の淵に立たされた思いがした。夢は音を立てて崩れた。まさか我が子に障がいがあるなんて。涙がとめどなく流れた。
一カ月検診のとき、隣の新潟県にある療育センターに行くことを勧められ、訪ねた。
そこで、障がいのある子を育てるには、施設で、親子一緒に訓練を受けるのが一番いいと、母子入所を提案された。
あいにく、地元にはそういった施設がなかった。気乗りはしなかったし、結婚したばかりの夫を一人残して家をあけるのもしのびなかったが、行くことに決めた。入所したのは、娘が生後十カ月頃ごろのことだ。
当時、私は小学校の教師をしていた。日頃、子ども達に語っていたことの一つが「人は人として尊い。どの子も、かけがえのない命なのだ」ということだ。
ところが、目の前の我が子に障がいがあるとわかった途端、この子は何のために生まれてきたのだろう、とすら思ってしまった。
親として子の誕生を喜べない、何とも情けない自分。子ども達に語っていたのは、きれいごとの薄っぺらい言葉に過ぎなかったのかと、自分が情けなくなった。
はりつめた心がやわらいでいく
療育センターに入所すると、今まで出会ったことのない、さまざまな障がいを持った子ども達がいた。
驚いたのは、母親達の明るさだ。入所したとき、私はおそらく能面のような顔をしていたのだろう。肩をポンポンとたたかれ、「力を抜いて。今日からよろしくね」と、気さくに声をかけてもらったのを覚えている。
次の日から、さっそくトレーニングが始まった。ダウン症の子は筋力が弱く、表情も口を開けてボーッとした感じで、身体もフニャフニャだ。最初からできなくても諦めず、辛抱強くトレーニングをくり返していった。
そのなかで、思ったこと、感じたことを日記に書いていった。大きな変化があるわけではないので、書くことはあまりない。
けれど、一週間、二週間、と過ぎていくなかで変化があるのは、娘ではなく、私だと気づき始めた。
夜、子ども達が休むと、母親だけの女子会の時間になる。こっそり夜食を食べながら、ワイワイとストレスを解消させるのだ。
ほかの人の話に耳を傾けていると、ここに来た当初は、私と同じように不安でいっぱいだったことがわかってホッとした。
みんなにも、辛くて泣いた日があったのだ。一気に肩の力が抜けた。そうだ、それが当たり前なのだ。
悩みを話し、おいしいものを食べ、私は少しずつ元気を取り戻していった。
私のはりつめた心がやわらいできたためか、娘の笑顔が増えた。いつも口を開けてボーッとした表情なのに、笑うと、ものすごくかわいい。
私が「バンザイ!」と両手を上げるまねをすると、娘も短い手を上げてバンザイをする。それもまたかわいらしい。
どの子も無限の力を秘めている
ある日、レクリエーションで、「手のひらを太陽に」をみんなで歌った。
「ぼくらはみんな生きている......
みんなみんな生きているんだ
友だちなんだ」
歌いながら涙が出てきた。懸命に生きている子ども達の姿は、なんて尊いのか。そんな想いが胸に迫ってきて、泣けて仕方なかった。
泣いている私を心配そうに、娘がまんまるな顔をグーッと近づけ、のぞきこんできた。悲しいんじゃなくて、うれしい涙だよ、と娘のほっぺをチョンチョンと押して伝えた。
療育センターに入所している子ども達の生きようとするエネルギーは本当にすごい。思い通りに動かない身体を補おうと、日々必死にトレーニングに励んでいた。小さな身体は無限の力を秘めているのだ。
あの子達に出会えて、私は「人は人として尊い」という言葉の重みを、命で感じることができた。それに気づかせてくれたことに、感謝の気持ちでいっぱいだ。
そして、あの明るい母親達は、今でも私の鑑だ。ありのままでいい。負い目を感じる必要などない。障がいのある子を育てるといっても、何も特別なことはない。
ゆっくり成長する我が子と、ゆっくり楽しみながら生きていけばいいのだ。
娘は、今年で二十七歳になる。まんまるな顔は、小さい頃のままだ。心やさしく、笑顔のかわいい娘は、私の宝物だ。