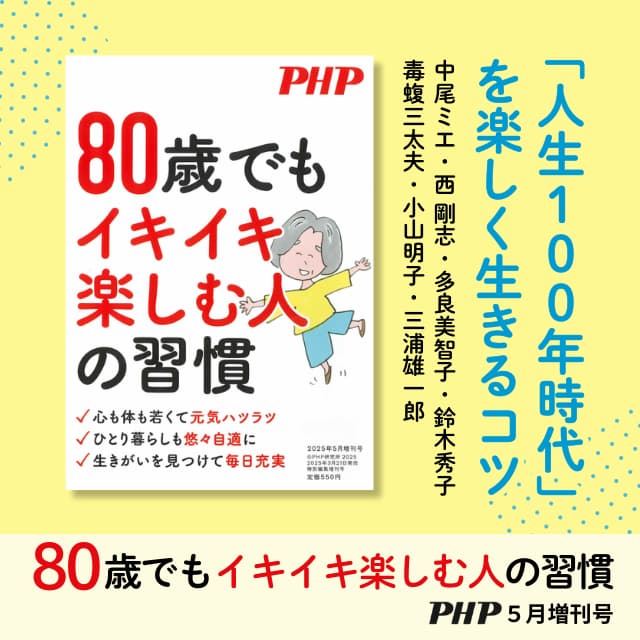松原惇子(まつばらじゅんこ)
エッセイスト。1947年、埼玉県生まれ。'86年、『女が家を買うとき』(文藝春秋)でデビュー。'98年『クロワッサン症候群』(同上)がベストセラーに。おひとりさまの「終活」を応援するNPO法人「SSSネットワーク」を立ちあげ、代表を務める。近著は『孤独こそ最高の老後』(SB新書)。
「これがわたし」。心からそう思えたとき、松原惇子さんの人生に光がさしました。
ほんとうにお恥ずかしい話だが、自分が何をしたら幸せなのかがわからず、かといって皆が目指す幸せを幸せだと思えない自分がいた。女性も働くのが当たり前の今の時代と、わたしの時代は違い、四年制大学に進学する女子も少なく、ほとんどの女子は、短大→ 結婚という道に、なんの疑問ももたずに進んで行った。
「結婚して子供ができれば、それはそれでいいものよ」とエリートサラリーマンと結婚した友人たちは、口をそろえて言う。経済の安定を得た彼女たちは、鬼の首でも取ったかのように、何の首も取ってないわたしに同情する。
同級生たちは、安定した生活のベルトコンベアに乗っていく。同じ年なのに、あちらは戸建てに住み、わたしは、風呂なしの六畳一間のアパート生活。新聞の求人欄を見るのが日課で、生活費を得るために履歴書を書いては面接に行っていた。
「平凡」を嫌い、「幸せ」を夢見ていた
そんなある日、パールのアクセサリーをデパートに出店していた元女優の小さな会社の秘書として採用される。しかし、秘書とは名ばかりで、女社長の犬の世話係。
女社長は当時四十代、わたしには顔のきれいなおばさんにしか見えなかったが、スタッフは女王さまのように扱っていた。
ある日、何が気に障ったのかしらないが、わたしは激しく叱咤された。今でいうところのパワハラだ。
ああ、ここはわたしのいるところではない。
「帰ろう」とバッグを握りしめ泣きながら、しけたアパートに戻った。なんの特技も強い願望もない自分。平凡な生活を嫌い、幸せを夢見ているわたし。これが二十代のわたしの現実だったのだ。
人と違う道を行くというのは大変なことだ。まず、自分を食べさせないといけない。そこからの出発だ。
今振り返ってみると、あんなに若くてぴちぴちしていたのだから、なんにでもチャレンジできたのに、なんで好きだったミュージカルの道に進まなかったのか悔やまれるが、そのときは、すでに人生に絶望していた。
自分を認めたとき、光がさした
そんなにっちもさっちもいかなかったわたしが、暗いトンネルから抜け出したのは、恥ずかしながら、本当に遅く、三十代後半だった。
きっかけは、わたしの不安定な生活を見ていた先輩から「シングルで生きていくなら自分の住まいだけは確保しろ。親に保証人になってもらいマンションを買いなさい」と言われたのだ。
そのとき初めて、わたしはこのどうしようもない自分を認めた。もう幸せ探しは終わりにしよう。誰に同情されてもかまわない。妥協できない自分を地味に生きていくわ。うれしいはずのマンションのカギを手にしたとき、涙が一気にあふれ出した。
こんなはずじゃなかったが、これがわたしなのだ。ああ、たいしたことないなあ。でも、これがわたしなのだ。心から、ちっぽけな自分を認めたとき、温かい光がさしこんだ。そのころの等身大の自分をつづった、『女が家を買うとき』(文春文庫)が思わぬ評価を受け、作家として生きていくよすがができたのだ。
正直、この年になっても、幸せがなんなのかわからないが、挫折としっかり向き合っていれば、いつか、光を感じるときが来る。これは自分の経験からはっきりと言えることだ。
挫折の原因はともかく、挫折したことのない人は、いないのではないだろうか。もし「挫折なんかしたことがない」という人がいたら、おそらく、その人は、傷つくことを極端に恐れているか、生まれつきものすごく鈍感な人のような気がする。
こうして、懐しい挫折したときの自分に戻り、エッセイを書いていると、挫折したことが誇りにさえ感じられる。