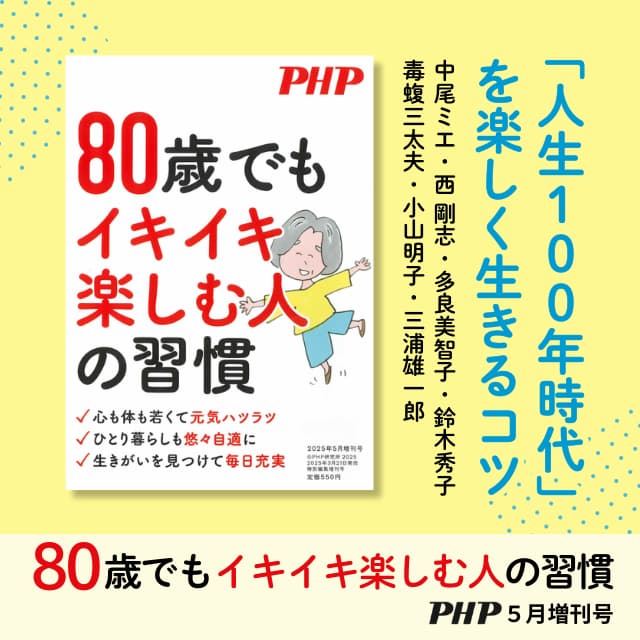第59回PHP賞受賞作
見澤富子
埼玉県所沢市・主婦・六十一歳
私には子宮がない。三十七歳で「子宮腺筋症」と診断され、子宮の全摘手術を受けた。
術後、私を襲ったのは、身体の痛みよりも激しい心の痛みだった。自分はもう、子どもを産むこともできなければ、お母さんと呼ばれることもない。やるせなかった。
自暴自棄になり、生活は荒れた。タバコやギャンブルに走り、消費者金融から借金もした。
「もう離婚しよう」
夫がそう告げてきたとき、目の前が真っ暗になった。夫まで失ったら、もう生きてはいけない。つらい気持ちに蓋をして過ごすしかなかった。
毎年お正月になると、子どもや孫の出生を知らせる年賀状が届く。見るたびに悲しみがこみ上げ、ポストの投函口をガムテープでふさいだ。
けれど、何をしても、何年経たっても、「子どもが欲しい」という思いだけは、私のなかで消えることはなかった。
そんな私に運命的な出会いが訪れたのは、五十歳のときだった。
市役所で「週末、短期里親」という制度を見つけた。夫と話し合い、研修を受け、翌年には「里親」の資格を取得した。共働きの私たちは、年に四回、長期休みに子どもを預かることになった。
わが家にやってきた女の子
忘れもしない、クリスマスの日。わが家に初めて三歳の女の子がやって来た。
子どもと過ごすというだけで、クリスマスの用意にも気合いが入った。ディナーのメインディッシュは焼鳥からローストチキンに、日本酒はシャンメリーに変わった。
初対面にもかかわらず、女の子は人懐っこかった。
「サンタさん、くるかなあ」
「はい、パパ、イチゴあ~ん」
「ママ、ギュウー」
夫の膝の上に座り、絵本を開いては「Xmas」を「バツバツ」と読んだ。そんな彼女の言動一つひとつが愛おしく、このまま時間が止まって欲しいとさえ思った。
こうして私たちは毎年、クリスマスを一緒に過ごすようになった。ご馳走やプレゼントを用意するのは、年に一度の楽しみだった。
しかし、私には一つだけ不安なことがあった。それは、彼女が私たちを「パパ」「ママ」と呼ぶことだった。
おそらく施設で「本当のパパとママではない」と教わっているはずだ。
「ママじゃなく、とみこさんってよんでね」
そう告げても、彼女は聞こえないふりをした。六歳になる年、私は彼女を座らせて話をした。
「ねえ、よく聞いて。お母さんは、あなたを産んでいないの。本当のお母さんは、ほかにいるのよ」
すると、彼女は目に涙をためて、しばらく動かなくなった。まずいと思ったときにはもう遅く、「おかあさんからうまれたかった!」と大声で泣き始めた。
彼女は「もしかしたら、この人たちが本当のパパとママかもしれない」と少しでも信じていたかったのだろう。
「ほんとうのママにあいたい」
散々泣いたあと、彼女は最後にそう言った。
その晩、夫と、彼女を養子として迎えたらどうかと話し合った。血のつながりはないが、共に過ごすうちに本当の親子になれる。私はそう感じていた。
目に見えないプレゼント
しかし、次のクリスマス、施設の職員の方から、女の子を引き取りたいという申し出が彼女の実母からあったと聞いた。
出産したころ、彼女の実母はシングルマザーで学生だったそうだ。ご両親の意向で、泣く泣く施設に入れたらしい。生活環境が整い、娘との同居を願っていた。
あまりにも唐突に、その年のクリスマスが彼女と過ごす最後の日になった。用意したチキンは涙で塩辛く、味がよくわからなかった。
撮った写真も、私は泣き顔ばかりだった。
にぎやかだったクリスマスは、もうやってこない。あの子の笑い声や音程のズレた歌声も、わが家で聞くことはない。
さびしさと同時に、彼女がいなくなって気づいた。目に見えるものだけがプレゼントではない。あの子と夫、三人で笑って過ごしたクリスマスは、とても幸せで、私へのプレゼントのような、大切な時間だった。
その後、母娘から年賀状が届いた。
幸せそうな母娘の写真と、少し成長した彼女からの「HAPPY NEW YEAR」というメッセージが添えられていた。
「Xmas」を「バツバツ」と読んでいた、あの子がこんなに立派になった。笑顔の"娘"を見ながら、私は安堵し、少し泣いた。