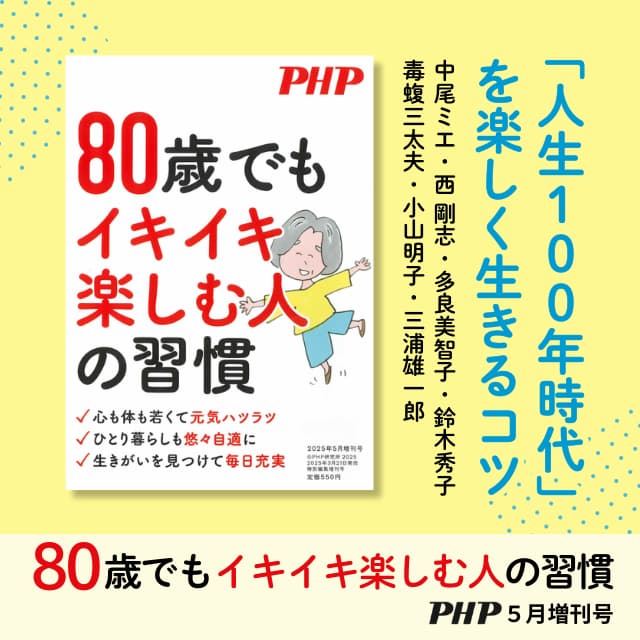第六十回PHP賞受賞作
森屋多美子
埼玉県東松山市・パート勤務・六十二歳
これは自慢話だ。他人の自慢話ほど耳障りなものはない。私もきっと顔をしかめるだろう。それでも書きとめておきたいのは、私にとってあの日が、かけがえのない宝物になったからだ。
昨年三月。卒業式の前日。式練習のあと、場を与えられて私はこんな話をした。
「明日は皆さんにとって、大切な日です。ただそれは、あなたたちだけでなく、お父さん、お母さん、先生方、友だち......。あなたたちに関わるすべての人にとっても、特別な日だということを忘れないでください。
――私にとってもです。あなたたちは、私にとって教師生活最後の教え子です。この三年間、共に過ごせたのが、あなたたちで本当によかった。一日一日が私の宝物です。自分のために、そして周囲の人たちのために、明日は最高の卒業式にしてください」
自分の定年退職について、これまで生徒全員の前で口にしたことはなかった。
土日もない生活で、走り続けた日々は苦しいことも多かったが、一片の悔いもない。幸せな教師生活だったと思う。だから再雇用も断った。あとはただ、最後の卒業式が無事に終わればいいと思っていた。
ところがだ。式練習が終わって職員室に戻り、ひと息ついていると突然、教務主任の先生が、血相をかえて飛びこんできた。
何やってんのよ、あんたたち
「森屋先生、大変だ。すぐ来てくれ」
三年生は今、各教室で最後のホームルームをしているはず。いったい何が起こったというのか。
「吹奏楽部の楽器の中から、とんでもない写真が見つかったんだ。該当者を音楽室に呼んで、今話を聞いている。早く!」
なんてことだ。ついさっき「明日は最高の卒業式にしよう」と言ったばかりなのに。頭の中で何かが崩れ落ちる音がした。
だが、仕方がない。とにかく事実を確認して、対応しなければ。
職員室を飛び出し、四階に向かった。音楽室は四階の一番奥だ。階段を上りきったところで、奥から、若い生徒指導担当の先生の怒鳴り声が聞こえてきた。
「おまえら、何やってんだ」
ああ、彼は今年初めて三年生を担任して、明日は本当に大切な卒業式だというのに......。彼が今まで一生懸命積み重ねてきたものの重みを考えると、悔しさが心の中に渦まく。
音楽室のドアに手をかけ、一気に開ける。
「何やってんのよ、あんたたち」
と言いかけたそのとき、目の前に広がった光景はあまりに鮮烈だった。
数人の生徒が、こちらを見ている。
数人? いや、違う。これは、三年生全員だ。
一瞬、わけがわからなくなった。
(全員が事件に関わってしまったのか)
瞬時、とんちんかんな考えが頭をよぎる。
だが、そんなはずはない。少し考えて、ようやくわかった。目の前にあるのは、生徒たちのあたたかな笑顔。隣で学年の先生方も微笑んでいる。その笑顔の一つひとつが、涙でかすんで見えなくなった。これはサプライズだ。仲間と生徒たちからの最高の贈り物だ。
生徒たちから幸せをもらっている
「これから、森屋先生の卒業式を始めます」
元生徒会長が、まっすぐな目で語りかけてくれた。教務主任の先生が「さあ、ここに」と、半円の中央にしつらえた席に私を促す。
卒業生の歌。全員合唱。ところどころ私へのメッセージを入れた替え歌になっていた。いったいいつ、この子たちはこんな練習をしたのだろう。音楽室いっぱいに響き渡った歌声は、今でも私の心の中で流れている。
花束を抱えた生徒が、「これ渡してしまったら、先生と本当にさよならなんですか?」と目を真っ赤にして言ってくれた。全員がそれぞれ、紙いっぱいに書いてくれた手紙の束も受け取った。これは絶対、私が死んだときに棺に入れてもらおう。
翌日は、卒業証書授与の介添えで壇上に立った私の腫れぼったい目に、生徒一人ひとりの顔がやきついて、涙腺は修復不能の崩壊状態だった。
学校現場は今、さまざまな問題を抱えている。ましてコロナ禍の子どもたちを思うと、心が痛い。去年と今年、何という違いだろう。
だが、どんなに苦しいときも、教師は教師であればいい。いつだって、生徒たちからたくさんの幸せをもらっていることを忘れずに。
あの日の記憶に上書き保存はしたくなくて、私はすっぱり教壇を去ったが、別の形で子どもたちとふれあいたくて、今は放課後デイサービスで仕事をしている。
あの日があったからこそ、今の私がある。生徒たちがくれた卒業式の思い出は、これから先の私の礎だ。