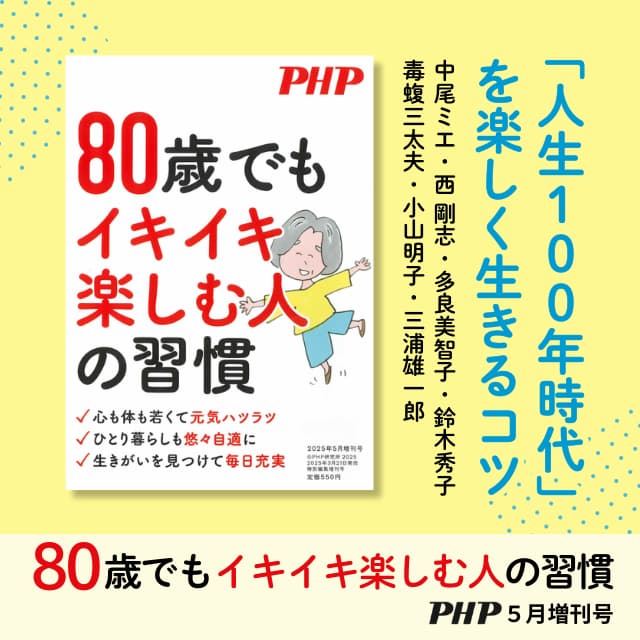第六十回PHP賞受賞作
小松崎有美
埼玉県所沢市・主婦・三十六歳
三年前、不妊治療をやめた。
足かけ九年。体外受精は十回以上。かかった費用は、総額一千万円以上。底をついたのは貯金だけではない。精神的にもどん底だった。「何もする気が起きない」と言いながら心療内科に通い、弱った心を薬でなだめた。
「わかった」
子どもを諦めたとき、夫はそれ以上、何も言わなかった。タバコを買いに行くふりをして出ていき、目を真っ赤にして戻ってきた。
最初からタバコを買うつもりなんてなかったのだろう。その証拠に、財布も車のキーも部屋のなかに置きっぱなしだった。
そんなどん底で見つけた光。それは、里親制度だった。市内報で里親募集を知ったのがきっかけだ。
子どもがほしい私たちには、何の迷いもなかった。突然家族が増えることにも、いずれ実親のもとへ返さなければならない現実にも、私たちの心は揺るがなかった。
およそ二年にわたる里親研修を経て、わが家に二歳の男の子がやってきた。何もない部屋に小さなタンスや布団が運び込まれると、部屋はたちまち喜びでいっぱいになった。
「ユミさんって呼んでね」
私たちが打ち解けるのに、そう時間はかからなかった。一緒にバッタをつかまえたり、しりとりもした。しりとりで、「ま」がくると、彼はいつも「ママ」と言った。「お」では「おかあさん」と言って、私を困らせた。彼はいつだって母親を求めていた。
ひと目でいいから
あれは、三歳になる誕生日のことだ。
施設から、実母が一緒に暮らしたがっていることを明かされた。顔では笑っていたが、心では泣いていた。しかし、断るわけにもいかなかった。彼が幸せになるのなら、むしろ受け入れるべきだと思った。
「ユミさん、またね」
小さな手を振りながら、彼は実母のもとへ帰っていった。
彼と離れてから、「ほんの気持ちです」と、私はお菓子や洋服を段ボールに詰めて送った。ひと箱が二箱になり、ついには三箱になった。
段ボールを送ると、その先で彼の喜ぶ顔が頭に浮かび、少し救われたが、次第に会いたい気持ちが強くなった。
「ひと目でいいから、会わせてもらえないでしょうか」
あるとき、段ボールに手紙を添えた。しかし、実母からの返答は意外なものだった。
「今回限りで贈り物はご遠慮願います。物心つく前に、こういったやりとりは控えたいと思っております」
私は言葉を失った。
しかし、実母は会う約束をしてくれた。これが最初で最後の面会。そうなることは、察しがついた。
約束の日、ベンチで待っていると、彼女たちがやってきた。私は駆けつけたい気持ちを抑えて、ゆっくりとベンチを立った。
通りすがりの知らない人を装うこと。それが今回の条件だ。
「こんにちは、坊や。ママと一緒でいいね」
「うん」
「ママが好きなんだねえ」
「うん!」
その言葉が胸に重く響いた。私の出る幕はなかった。
実母は、すぐにでもこの場から去りたがっている様子だった。
「さ、帰るよ」
実母が手を引いた、そのときだった。
きみの幸せを心から願う
「おばちゃん、一本あげる。さっき見つけたんだよ」
彼は、持っていた花を私に手渡した。それは、まだ蕾のカーネーションだった。
まもなく公園をあとにした二人を、本当なら見えなくなるまで見ていたかったが、涙が視界をふさいで見届けることができなかった。
公園からの帰り道を、とても長く感じた。行く先々で何人もの人とぶつかり、クラクションの音も車から飛び出す怒号も、どこか他人ごと。このまま事故に遭ったら、彼らが飛んできてくれるんじゃないか。そんな馬鹿なことまで考えた。
帰宅して、カレンダーを見て知った。
今日は母の日だったのだ。
結局「ママ」とは呼ばれなかったし、母親らしいこともできなかった。あれだけ濃厚な時間を過ごしても、子どもの記憶にはこれっぽっちも残らなかった。残ったのは、花一輪。
だけど、この花を今日受け取った意味は、きっとあると思った。
たとえ血がつながっていなくても、きみの幸せを心から願う人がいるんだよ。この想いが、彼に届きますように。