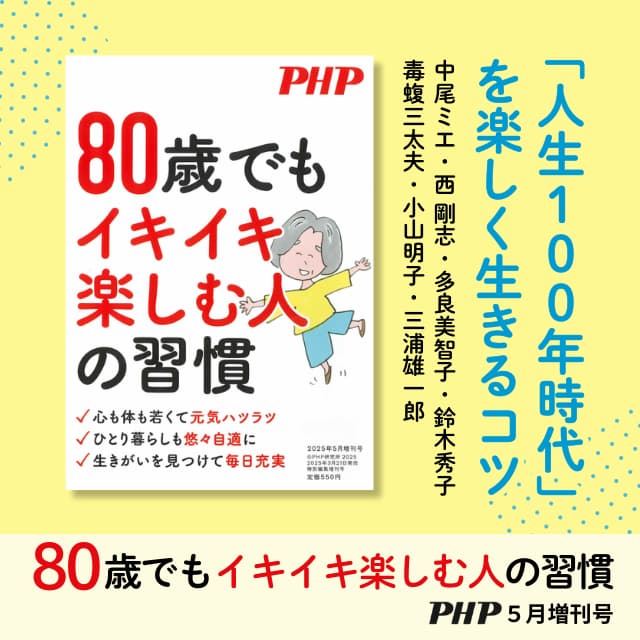南杏子(医師/作家)
1961年、徳島県生まれ。日本女子大学卒業後、出版社勤務を経て結婚。英国へ転居し、海外出産を経験する。帰国後は東海大学医学部に学士編入。2016年に作家デビューし、'21年『いのちの停車場』(幻冬舎文庫)が映画化された。近著は『アルツ村』(講談社)。
やりたいと思ったときに動いてみる。自分の人生に遠慮する必要はありません。
・女子大を卒業したものの就職浪人。
・何とか編集者になって、約10年。
・33歳で医学生、38歳で医師。
・55歳で小説家デビュー。
......こうした興味と関心の向くままに人生を歩む自分の姿は、子どもの頃には想像もできませんでした。
どちらかというと大人しく、周囲を驚かさない、期待に沿って生きる子どもでした。
洋裁好きな専業主婦の母と繊維会社に勤務する父に育てられ、家族の会話も洋服や繊維に関してのことが多い日々。「女の子だし大学に行かなくていい」と言われましたが、勉強は好きだったので受験し、学費を出してもらいました。進学先に選んだ家政学部被服学科は興味のある分野だっただけでなく、家族から大いに歓迎されました。
大学に行くために上京し、祖父母の家から通学することになりました。行って初めて気づいたのは、脳梗塞の後遺症から寝たきりとなった祖父を祖母が世話する、今で言う「老老介護」の状況でした。介護保険制度ができたのは2000年のこと。私が大学生の頃は、「介護は家族が行なうもの」というのが常識で、否応もなく介護を手伝う生活が始まりました。今で言うヤングケアラーです。「女の子だから家事手伝いや祖父母の世話をする」という風潮に私自身も従順でした。
そんな頃、大学で女性問題を考える講座に出会いました。私は、生まれて初めて自分の日常に疑問を抱くようになったのです。
雇用機会均等法が施行された1986年より前の就職活動では、女子大生というだけで門前払いされることも当たり前でした。就職は結婚相手を見つけるのが目的と考える女性も少なくない時代でもあったのです。
編集者、医師、そして作家に
働くに際しては、自分の目を開かせてくれた本のために生きてみたい――編集者になろうと考えました。ところが新卒の年、大手から中小まで受けた出版社はあえなく全滅。「女性は採用なし」「指定の大学からしか採っていない」などなど理不尽と思う理由もありましたが、自分自身の実力不足も痛感し、編集者への憧れはますます増したのです。結局、出版社の下請け業務を請け負う小さな編集プロダクションの求人広告を新聞で見つけ、何とか社会人としての人生がスタートしました。両親からは「一体何を考えているの」と驚かれました。
やがて大手出版社の育児雑誌編集部へ中途入社がかない、そこで勤務している間に子どもを授かりました。当時、始まったばかりの産休・育休制度を利用させてもらい、夫の英国留学に同行する形で、海外出産・育児を行ないました。現地で大学の語学コースなどに通いながら、30代、40代の英国人学生や留学生たちと友人になったのです。
これも今では当たり前にあることだけれど、「年を取ってからでも勉強していいんだ」と、目からうろこが落ちる思いでした。
その後、日本に帰国して医学部を受験し、幼い頃から勉強したかった医学を学ぶチャンスを得ました。医師といえば、男性――そんな思い込みを逆手に取るクイズがあったくらい、子ども時代には考えられなかった進路を、30歳を過ぎてからスタートさせました。
この決断には、夫をはじめ周囲の理解が大きく影響しました。送り出してくれた出版社にも、長女の世話を引き受けてくれた両親にも大恩があります。「あなたがそんなに勉強が好きだったなんて、知らなかった」と両親はやっぱり驚いていましたが。
自分で自分を縛らない
毎日の診療では、患者さんに感謝されることに支えられて夢中になって働き続けています。自分が選んだ高齢者医療の仕事を通じ、社会のために尽くせる機会に恵まれて、私のほうこそ感謝の日々です。
そして、10年ほど前から小説を書き始めました。かつて自分が勇気づけられたように、誰かの心に届く物語を書きたくなったのです。医師として患者さんやご家族の深い言葉に触れるたびに、「一人だけのものにしておくのはもったいない」と思うようになり、それが私の小説の大きなテーマです。
ここ最近は、「私なんて」という思いを意識的に捨てることにしました。人は社会の目を気にして、いつの間にか自分で自分を縛ってしまうものです。「私は女性だから」「いい年をして」。他にも「柄にもなく」「素人のくせに」などなど。さらには、「自分のことは、よくわきまえております」というポーズを取るため、せっかくチャンスがあっても、「私なんて」と遠慮してしまいがちです。
そんなことで、学びたかったこと、やりたかったこと、立ちたかった舞台を逃してしまうのは、もったいない生き方ではないかと思うのです。「私なんて」は、人生をつまらなくしてしまいます。
自分の気持ちが向くものに出会えるチャンスは、そうそう巡ってこないものです。いざ出会えたら、迷わずチャレンジしてほしい。そしてもし、あなたがチャンスを与える側にいるのなら、広く門戸を開く人になってほしいのです。それがさらに多くの誰かに役に立つかもしれないのですから。