雑誌
THE21 2021年10月号
今月号の読みどころ
本を読んで学びたくても「読んだ内容を忘れてしまう」という悩みがよく聞かれます。せっかく読書をするなら、その内容を何とかして定着させたいですよね。そこで今回は、「身になる読書」とはどういう読み方なのかを追究しました。「楽しむ」ことと「学び」を両立させる読み方を、ぜひ参考にしてみてください。
| 公式サイト | 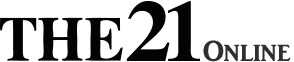 |
|---|
今月号の目次
総力特集:頭がいい人の読書術
|
<第1部>人生を豊かにする本の読み方 |
||
|
楽しんで読み、アウトプットすることで知識を自分のものにする |
||
|
「面白い×役に立つ」を両立させるコンサルタントの本の選び方 |
御立尚資 |
|
|
本をきっかけに自分を客観視すれば、新しい世界が開かれる |
山口真由 |
|
|
小説や経営書が教えてくれる問題解決のヒント |
米女太一 |
|
|
「楽しむ」ための読書こそ結果として学びにつながる |
今井むつみ |
|
|
<第2部>「学び」を使えるカタチにするアウトプット読書術 |
||
|
「削ぎ落として整理」すると、読んだ内容の理解が深まる |
葉一 |
|
|
「自分の足跡」を残しながら読み、必ずアウトプットする |
アバタロー |
|
|
どんな本でも学びを最大化する「視点×法則読書」法 |
羽田康祐 |
第2特集 今、注目の「サステナブル経営」とは?
|
持続可能なビジネスに変える国内外の先進企業事例 |
村上 芽 |
|
|
SDGsの実践は中小企業が生き残る鍵になる |
泉 貴嗣 |
巻頭特別インタビュー
|
僕らの世代は、世代を超えてタッグを組むためのパイプ役になれると思います |
ムロツヨシ |
特別企画
|
仕事に役立つ「デザインクイズ」で売れるデザインがわかる! |
ウジトモコ |
TOPICS
|
「言いたいこと」がちゃんと伝わる読まれる文章の書き方 |
尾藤克之 |
|
|
販売台数前年度比125%を達成した京都トヨタの「会議」改革 |
芳賀将英×田近秀敏 |
|
|
注目のリラックススポット&アイテムで日常に豊かな感性を |
||
|
仕事の成果が大きく変わるテレワークのチーム運営 |
福山誠一郎 |
|
|
テレワークがうまくいっている企業は、どのように取り組んでいるのか? |
連載 ほか
|
悩めるマネージャーに伝える「部下指導で一番大切なこと」 第1回 Z世代の新入社員の価値観に合わせるべきか? |
丹羽宇一郎 |
|
|
ビジネスパーソンのための「アート思考」トレーニング 第1回 ミリアム・カーン《美しいブルー》 |
末永幸歩 |
|
|
図解で深掘り! 時事ワード 第10回 オリンピックのビジネスモデル |
近藤哲朗 |
|
|
私のターニング・ポイント 第82回 日本最高齢のフィットネスインストラクターへと導いたトレーナーとの出会い |
瀧島未香 |
|
|
「男らしさ」の呪縛 第5回 定年後誤算 |
奥田祥子 |
|
|
カレー沢薫の明るい悩み相談室 第22回「ノルマ達成のプレッシャー」とのつきあい方 |
カレー沢薫 |
|
|
心をつなぐ英語表現ワンフレーズ 第7回「もうひと踏ん張り!」 |
松本祐香 |
|
|
オネエ精神科医Tomyのお疲れメンタルクリニック 第10回「嫌いな上司」のお悩み |
Tomy |
|
|
老舗企業トップに聞く「不易流行」の経営 第10回 社訓「売るよりつくれ」を新解釈。創業200年を超えて、21世紀に大きく成長した理由 |
渡辺雅司 |
|
|
この本の著者に話が聞きたい! 第10回『企画』 |
高瀬敦也 |
|
|
商品に歴史あり 第334回「サトウのごはん」 |
藤井龍二 |
|
|
あの“ビジネススキル”を試したら 第82回「2.5倍速の効果」の巻 |
ichida |
|
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 Concept & Message |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 今月のキーフレーズ |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 今月のキーポイント3 |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 読者からのおたより/『THE21』から生まれた本 |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 次号予告/編集後記 |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 定期購読のご案内 |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 「THE21オンライン」のご案内 |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 読者プレゼント&インフォメーション |
||
|
「仕事に使える」ビジネス情報源 編集長の気になるエンタメ情報 |
THE21 とは
実力主義時代のいま、ビジネスマンには仕事の能力やスキルをアップさせることが強く求められています。月刊誌『THE21』ではその要請に応え、(1)いま話題のビジネス・スキルをやさしく解説するとともに、(2)第一線で活躍しているビジネスパーソンのプロのノウハウを紹介するなど、「いますぐ使える仕事術」が満載されています。それに加えて、(3)いまさら人に聞けない基礎知識や、(4)最低限抑えておきたい最新トピックスも提供し、ビジネスマン必読の情報誌づくりをめざしています。昭和59年10月の創刊以来、ビジネスマンを中心に幅広い年齢層で大きな反響を呼んでいます。


















