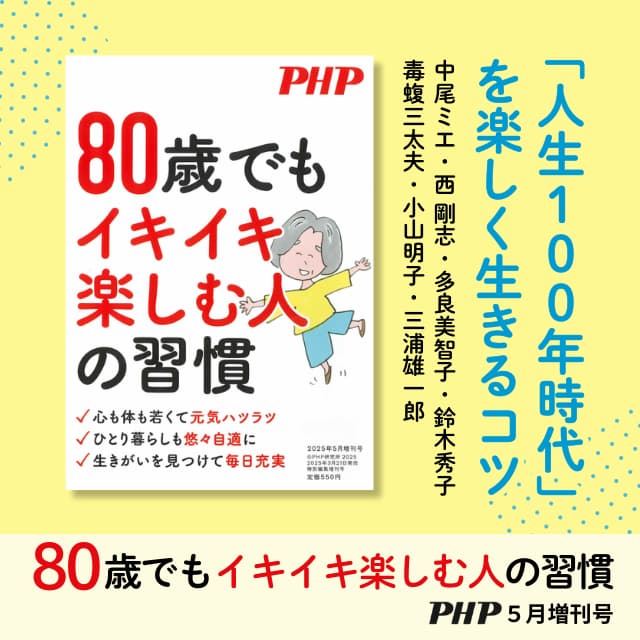第69回PHP賞受賞作
川端七成
東京都・会社員・27歳
自転車がパンクした。1年前のことだ。出発しようとしてすぐに後輪からパンッという音がして、ペダルをこぎ出してから「ああ、やっぱりパンクか」と現実を受け入れた。買ってからまだ3カ月も経っていない。ひとまず、近くの自転車屋に駆け込むことにした。
こぢんまりとした商店街にある小さな自転車屋さんに到着すると、店先でおばちゃんが一人、外をぼうっとながめながら佇んでいた。「あのう......」と声をかける。彼女は私と、私の自転車を一瞥して、すぐに「パンク?」と気づいてくれた。優しそうな人で安心した。くるくるとタイヤを回し、どこから空気が抜けたのかを調べてくれる。
するとおばちゃんは「いたずらかねえ」と、ある1点を指差した。見てみると、タイヤに太い釘のようなものがざっくり刺さっていた。そうか、いたずらの可能性があったのか。そう気づいたら、刺さった釘の太さが妙に生々しく感じられた。「なおすの、見てる?」と言いながらパイプ椅子を出してくれたので、ありがたく座らせてもらうことにした。
怖かった。いたずらと決まったわけじゃないし、偶然刺さってしまった可能性もある。それでも、誰かに悪意を向けられているかもしれないという状況が、とても恐ろしかった。
おばちゃんはタイヤをじっとながめ、「これはダメかもしれないねえ」と言って、奥にいる旦那さんを呼びに行った。待っている間、「そうか、もうダメなのか」と、知っている気持ちをたどるように思った。別に大した自転車じゃない。2万円のただのママチャリだ。友達からは「電動じゃないのかよ」と笑われた。それでも私は気に入ってたんだけどなあ、とさびしい気持ちになった。
大丈夫な日も、大丈夫じゃない日も
当時、私は職場の人間関係が原因で適応障害を患っていた。心が疲弊し、うまく起きられなくなって約2カ月。何もできない日々の中で唯一、自転車に乗ることは楽しかった。新宿、渋谷、高円寺、阿佐谷、二子玉川、吉祥寺、いろんな場所へ行った。大丈夫な日も、大丈夫じゃない日も、私は自分の足でペダルをこいで、行きたい場所へ行けた。
それがもう、できなくなってしまうのか。自転車がダメになってしまったのだ。私ももうダメだし、これから先どこにも行けないんだな。そんなことを思いながら、いろんなことのあきらめ方をずっと考えていた。
店の奥から店主のおじちゃんが出てきて、タイヤをじっとながめ、ごそごそと動き始めた。自転車屋さんなんてめったに来ないから、足元に散らばっている未知の器具が、どれもかっこよく見えた。タイヤの空気を抜き、丁寧に釘を抜いてくれる。釘を取り除くと、タイヤにはぱっくりと丸い穴が空いていて、「中のチューブもダメになってるんじゃない?」とおばちゃんがつぶやいた。やっぱりダメだよなあ。おじちゃんは黙ったままだった。
タイヤからチューブを抜き取り、奥から持ってきた道具箱を開くと、おじちゃんは修理用の液体やテープを、穴が空いた部分に、丁寧に指の腹を使って塗り、貼っていった。穴をふさぐ作業を終え、修理したチューブを水にさらしたあと、それをタイヤの中へと戻していく。空気を入れ直し、ついでに前輪のタイヤにも空気を入れてくれて、気づいたら自転車は元通りになっていた。
彼が丁寧に、ゆっくり、でも着実に、自転車をなおしていく過程を私はじっと見ていた。見ながらずっと、泣きそうだった。全然ダメじゃなかった。丁寧に人の手で修理をすれば、ちゃんと元通りになるものがあるし、また走れるようになる日が来るのだと思った。
自分の足でペダルをこいで
「1200円です」と、おじちゃんがはじめて言葉を発した。無口だから怖い人だと思っていたけれど、思いのほか優しい声色だった。いつもだったら「こんなことでお金を使ってしまった」「ついてない」と絶望していたかもしれない。でもその日はそんなことまったく思わなかった。むしろ前向きな、1200円。
「こんなにあったかい日、久しぶりじゃない?」おばちゃんが言って、2人で店の外まで見送ってくれた。ペダルをこぎ出すと、昨日までよりずっと推進力があった。春の訪れを感じる陽気の中、体が前に、前に進んで、風が心地いい。私はまだ、大丈夫だと思った。全然ダメなんかじゃない。自分の足でペダルをこぐために、私はこれから、私の大事なものをゆっくりなおしていくんだ。ただ、そのための春が来たのだった。
今年もまた、春が来る。ペダルをこぎ、あたたかな風を切って走るたび、何度でもあの日のことを思い出す。あの春、一度壊れて、そしてなおした自転車と私自身で今、春の訪れを胸いっぱいに抱きしめている。