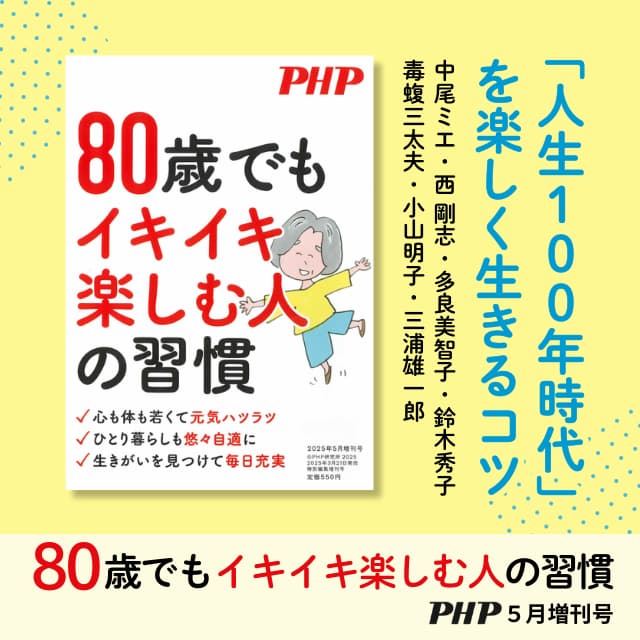第70回PHP賞受賞作
木南木一
福島県・公務員・34歳
大学生のころ、僕は福島の現状を知るために、大学の仲間とボランティア活動に参加した。被災地の中でも福島は原子力災害という特異性を抱えていた。
がれきの撤去や住宅再建などの物理的な復興だけではなく、放射線への不安、土地の利用制限、生活の再構築――課題があちこちに横たわっていた。現実を目の当たりにして、強く思った。福島の力になりたいと。ただ直感的に、漠然とした義務感とともに。
福島に足を踏み入れた最初の日、駅前の小さなバス停で立ちすくんだ。空気は澄んでいて、でも湿度のせいか重く感じられた。僕の心は揺れていて、何をどうすればいいのかわからなかった。ただ目の前にある現実が、言葉にならない問いを投げかけてきた。僕は、大学を卒業後は福島県に行くと決めた。
福島の町で働き始めた当初は、被災地支援に直接関わることばかりを想像していた。がれきの撤去現場や仮設住宅の訪問、支援物資の配布――現場に立って、汗をかきながら人々の役に立ちたいと考えていた。
しかし、現実はもっと微妙で、静かだった。日々、庁舎の中で書類に目を通し、会議に参加し、数字を検証することに追われる。被災地に来たからといって、直接的に復興に手を貸せる仕事ばかりではないのだととまどった。自分のやりたいことと、実際の仕事との距離感に、何度ももどかしさを覚えた。
しかし、ある日ふと気づいた。自分の仕事の一つひとつが、復興の流れの中で小さな歯車となっていることを。
目に見えない小さな努力が
震災から10年目のある冬の日、僕は駅前の商店街を歩いていた。新しい店が開き、古い建物が改修され、子供たちが走り回っていた。僕が関わった仕事の中に、直接的にこれらの変化を生み出したものはほとんどない。
小さな努力は、長い時間をかけて、町の空気や街路樹の揺れ、子供たちの笑い声に浸透していく。僕が庁舎でこなす仕事は、派手ではないし拍手も喝采ももらえない。それでも、誰かの生活の安定や安心につながっていることを、僕は知っている。日々の仕事の一つひとつが、目に見えないネットワークを編む糸であり、その糸は確実に町の未来へとつながっている。
福島で働く日々は、少しずつ変化する風景や、人々の笑顔に気づくことの大切さを教えてくれた。復興とは、劇的になしうるものではなく、静かで確実な変化の連続であることを理解した。仕事を通してその変化の一部になることが、僕にとっての支援であり、貢献であるのだと知った。
これからも福島で働いて生きていく
僕はまだ、福島でやりたいことのすべてを達成できたわけではない。直接的に被災者の生活を救うわけでもないし、ドラマチックな瞬間に立ち会えるわけでもない。
時々、被災地支援に関わるほかの人々の活動を目にすると、焦る気持ちがよぎる。彼らは目に見える形で力となり、手応えを感じているのだろう。それに比べて自分の仕事は静かで、地味で、存在感の薄さに耐えなければならない。それでも、自分の存在が、復興の歯車の一つとしてたしかに回っていることを信じている。その信念は、じわじわと僕の心を満たしてくれる。
仕事は教えてくれる。結果だけが価値ではないことを。目に見える手応えだけが報酬ではないことを。大きな物語の中で、自分の存在は小さく見えるかもしれない。しかし、小さな存在でも、たしかに物語に影響を与えていることを。福島の町が少しずつ光を取り戻す中で、僕はそのことを日々実感している。
これからも僕は、この町で、静かに、しかし確実に働き続けたい。目立たない歯車であることに誇りを持ち、復興を支えていきたい。そして、いつか振り返ったとき、あの冬の日の駅前で感じた漠然とした義務感が、たしかな力となって町の未来に息づいていることを感じられるように、僕は今日もペンを走らせ、書類に目を通し、会議に参加する。
仕事が教えてくれたこと。それは、力の大きさではなく、続けることの価値。小さな努力の積み重ねが、やがて大きな変化を生むこと。微力でも、たしかに何かの一部になれること。僕はこの町で、そのことを知り、実感し、これからも生きていく。