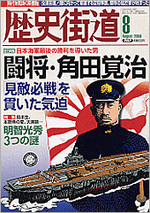雑誌
歴史街道 2008年8月号
今月号の読みどころ
「戦う時は徹底して戦う」。それが海軍中将角田覚治の信念でした。その真価が最も発揮されるのが、昭和17年(1942)10月の南太平洋海戦です。ミッドウェー海戦の敗北より4カ月、雪辱を期す南雲長官率いる機動部隊の4空母は、再び米機動部隊と決戦の時を迎えます。しかし、またも2空母が被弾、無念の南雲長官は指揮権を角田に託しました。「全速前進!」角田は自らの空母を敵へ突進させます。敵に接近して反復攻撃をかける「肉を切らせて骨を断つ」戦法でした。この闘志が敵空母を撃沈、撃破させ、勝利をもたらします。気迫溢れる戦い方は角田の生き方でもありました。日本海軍きっての闘将の気迫を描きます。
第二特集は明智光秀、3つの謎です。
第二特集は明智光秀、3つの謎です。
| 公式サイト |  |
|---|---|
| YouTube |
 |
今月号の目次
|
見難必救 |
黒鉄ヒロシ |
3p |
|
この人に会いたい vol.19 |
原田佳奈 |
7p |
総力特集 日本海軍最後の勝利を導いた男 闘将・角田覚治
|
総論 「見敵必戦」の気迫と、部下への温情を兼ね備えた闘将 |
戸高一成 |
14p |
|
ビジュアル1 闘将の猛反撃、始まる |
20p |
|
|
ビジュアル2 再び激突! 日米機動部隊 |
22p |
|
|
ビジュアル3 太平洋の波濤を越えて |
24p |
|
|
即座に攻撃隊発進! 龍驤単艦でドールマン艦隊十三隻に挑む |
亀井宏 |
26p |
|
コラム1 北の涯、アリューシャンへ |
31p |
|
|
「各艦、探照灯つけ」 荒天のダッチハーバー沖で示した部下への思い |
秋月達郎 |
32p |
|
コラム2 部下に優しかった闘将 |
37p |
|
|
ビジュアル4 日米海軍の天王山、ソロモン海の激闘 |
38p |
|
|
「只今より航空戦の指揮をとる」 最後の勝利を呼んだ南太平洋海戦 |
松田十刻 |
40p |
|
コラム3 山本長官との永別 |
49p |
|
|
ビジュアル5 攻撃に次ぐ攻撃! 南太平洋海戦の死闘 |
50p |
|
|
優しく家族思いだった父の素顔 |
青山文子 |
52p |
|
「この人が機動艦隊を率いていれば」 航空参謀が見た艦橋の司令官 |
奥宮正武 |
54p |
|
コラム4 全軍の輿望を担って |
59p |
|
|
「抗命の罪はこの角田が負う」 テニアン島で最後まで闘志を失わず |
野村敏雄 |
60p |
|
グラフィティ にっぽんの剣豪 83 草深甚四郎 |
本山賢司 |
66p |
|
CGで再現! 江戸はこんな町だった |
68p |
|
|
時の迷路―明治・大正・昭和篇 養蚕農家 |
香川元太郎 |
74p |
特集 前半生、本能寺の変、天海説… 明智光秀、3つの謎
|
一介の浪人がなぜ将軍や信長に認められたのか |
楠戸義昭 |
78p |
|
本能寺の変の動機は怨恨か、野望か、黒幕はいたのか |
河合敦 |
82p |
|
ビジュアル 各地に残る足跡と伝説 |
86p |
|
|
明智は死なず? 光秀天海説はなぜ生まれたのか |
中津文彦 |
88p |
|
コラム 親族たちの不可解な「その後」 |
92p |
|
|
|
||
|
大和ミュージアム館長が語る日本海軍士官の証言 第七回 三原 誠 マリアナ沖海戦を戦った整備科予備士官 |
戸高一成 |
94p |
|
「皇居周辺」の銅像をめぐる |
100p |
|
|
歴史街道クイズ 「戦国検定!」 |
102p |
|
|
アイゼンハワーが震えた日 ドイツ軍最後の攻勢と暗殺計画 後編 |
吉田一彦 |
104p |
|
「歴史街道」伝言板 |
110p |
|
|
BOOKS・CINEMA |
112p |
|
|
この著者に注目! 渡辺利夫 |
114p |
|
|
人物で語る日本近代史 第三回 岩倉具視と大久保利通 近代日本を生み出すための謀略 |
中西輝政 |
116p |
|
谷沢永一の「日本史ヤミ鍋」 84 士族と平民とを区別された経緯 |
谷沢永一 |
122p |
|
日本を変えた古代史10大事件 第9回 歴史の転換点となった大津皇子の死 |
関裕二 |
125p |
|
歴史街道・ロマンへの扉 醒井 |
鶴田純也 |
134p |
|
江戸のスイーツを食べ歩く 第7回 東日暮里・羽二重団子本店 羽二重団子 |
岸朝子(選) 逢坂剛(筆) |
136p |
|
日本ふるさと紀行 城下町を訪ねて 第6回 兵庫県豊岡市・出石 |
中塚裕(写真)七森武倫(文) |
141p |
歴史街道 とは
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。