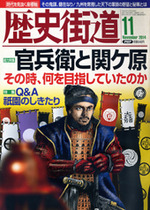雑誌
歴史街道 2014年11月号
今月号の読みどころ
「黒田官兵衛が大坂方と通じれば、加藤清正は喜んで味方になるはずだ。その他の九州大名の島津義弘・鍋島直茂・立花宗茂はいずれも大坂方なので、結束して官兵衛と清正を中心に東上すれば、中国地方の軍勢も加わって十万騎にはなる。これだけの大軍で戦えば、徳川家康はひとたまりもない…」。黒田長政はそんな内容を遺言状に記しました。慶長5年(1600)、天下分け目の決戦に向け風雲急を告げる中、遥か九州で情勢を虎視眈眈と窺っていたのが、「天下の軍師」黒田官兵衛です。東軍に与した官兵衛は寄せ集めの兵を率い、九州を席捲。さらに広島を奪う壮大な計画を立てていました。果たしてその狙いとは。官兵衛が最後の戦いで目指したものを探ります。第二特集は「Q&A 祇園のしきたり」です。
| 公式サイト |  |
|---|---|
| YouTube |
 |
今月号の目次
|
官兵衛して |
黒鉄ヒロシ |
3p |
|
この人に会いたい vol.94 |
有村架純 |
7p |
総力特集 官兵衛と関ケ原 その時、何を目指していたのか
|
総論 九州は切り取り次第! 軍師でなく武将として戦国魂を示す |
小和田哲男 |
14p |
|
九州を、そして天下を振り回してのけた官兵衛の強かさを伝えたい |
岡田准一 |
20p |
|
松坂桃李が語る長政にとっての父・官兵衛、そして関ケ原 |
23p |
|
|
ビジュアル1 黒田父子を取り巻く人々 |
24p |
|
|
朝鮮出兵と秀吉の死…天下が再び揺らぐ中、父子はそれぞれの道へ |
江宮隆之 |
26p |
|
コラム1 長政はなぜ家康に接近したのか |
31p |
|
|
ビジュアル2 官兵衛と長政、それぞれの思惑と選択 |
32p |
|
|
「一次史料」と「二次史料」から読み解く官兵衛の実像 |
34p |
|
|
コラム2 中国国分以来の毛利家との縁 |
37p |
|
|
毛利を味方に…吉川広家への書状が示す黒田父子のスタンスの違い |
渡邊大門 |
38p |
|
コラム3 福岡城の瓦に刻まれた十字架 |
43p |
|
|
「天下惣無事」崩壊…九州を切り取り、第三極のキーマンを目指す |
橋場日月 |
44p |
|
コラム4 調略で呼び込んだ関ケ原の勝利 |
49p |
|
|
年表・深謀と席捲! 官兵衛の関ケ原 |
50p |
|
|
栗山・母里・井上の三家老と又兵衛…黒田家の柱石となった男たち |
本山一城 |
52p |
|
無血開城で敵を自軍に! 石垣原の決戦と九州席捲の鮮やかな采配 |
工藤章興 |
56p |
|
ビジュアル3 軍師、再び起つ! 破竹の九州平定戦 |
62p |
|
|
九州平定後に中国へ…戦国の論理が甦る中、何を目論んでいたのか |
渡邊大門 |
64p |
|
|
Q&A祇園のしきたり 伝統が息づく京都の奥座敷入門
|
第一部 舞妓さんと芸妓さんの違いは? 祇園の成り立ちと常識 |
柏井 壽 |
78p |
|
ビジュアル 芸舞妓が彩る祇園の年中行事 |
84p |
|
|
第二部 「一見さん」でも遊べるの? 花街の風情を愉しむ |
柏井 壽 |
86p |
読み物&連載
|
堺の鉄砲を生んだ貿易都市の商魂と技術 |
二宮 要 |
69p |
|
弾丸列車から新幹線へ…島秀雄と男たちの夢 |
秋月達郎 |
122p |
|
|
||
|
XX ダブルクロス 史上最大の欺瞞作戦 第4回 必要なものしか与えずに満足させる |
吉田一彦 |
94p |
|
我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記 立国篇 第18回 |
海道龍一朗 |
100p |
|
大東亜戦争写真紀行 世界で感謝された日本人 第7回 同盟国として共に戦った「微笑みの国」・タイ |
文・写真 井上和彦 |
116p |
|
お江戸ぶらり散歩 あの日、あの時、この場所で 第8回 江戸大洪水 |
文・絵 堀口茉純 |
126p |
|
歴史街道・ロマンへの扉 赤穂城 |
林宏樹 |
134p |
|
江戸の料理再現づくし 第27回 なんきん粥・淡雪はんぺん |
向笠千恵子 料理再現・福田 浩 |
136p |
|
近江花伝 第10回 蒲生野 白洲正子の愛した近江 |
写真・文 寿福 滋 |
141p |
|
|
||
|
「歴史街道」伝言板 |
110p |
|
|
BOOKS・CINEMA |
112p |
|
|
この著者に注目! 田中秀雄 |
114p |
|
|
歴史街道脇本陣 |
131p |
歴史街道 とは
「いま、歴史がおもしろい」
歴史は過去の人物や出来事を取り上げるとはいえ、現代の人びとに役立たなければ意味がありません。また、歴史は本来、そんなに堅苦しく難しいものではなく、もっと身近で楽しいものであるはずです。そして何より、人間を知り、時代の流れを知る上で、歴史ほど有益な参考書はありません。そこで『歴史街道』は、現代からの視点で日本や外国の歴史を取り上げ、今を生きる私たちのために「活かせる歴史」「楽しい歴史」をビジュアルでカラフルな誌面とともに提供します。いわば、新しいタイプの歴史雑誌といえるでしょう。