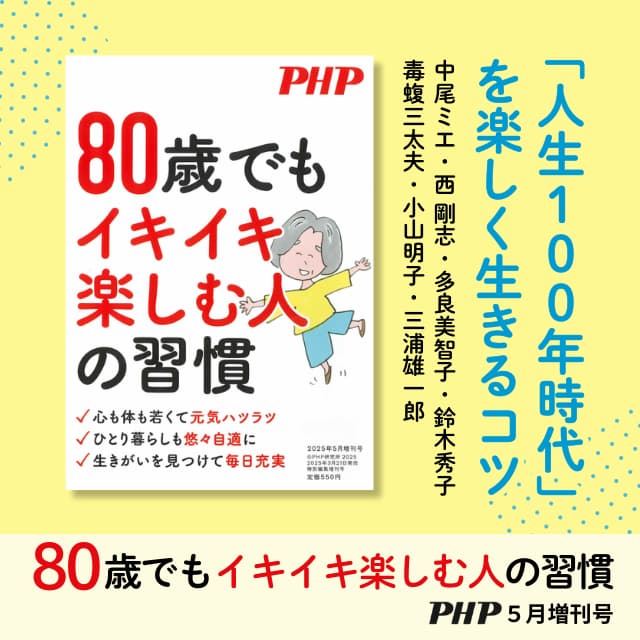第68回PHP賞受賞作
越田恵子
石川県・パート・68歳
「あら、越田さん、どうしたの」
かけられた聞き覚えのある声にハッとしてうつむいていた顔を上げると、そこには尊敬する元勤務先の先輩が、いつものおだやかな表情で立っていました。場所は大学病院の待ち合い室。10年ぶりの再会の場所が大学病院であったことに、とてもおどろきました。
私は当時、10万人に一人という難病にかかっていることがわかり、体の痛みとともに、有効な治療方法がなく、治らないという現実に打ちのめされていました。出会った場所が場所なので、彼女も簡単な病気ではないのだろうということは、容易に見当がつきました。
彼女はがんで、1年ほど前に手術をして入院していたこと、抗がん剤の副作用で髪もまつげも抜けてしまったこと、手のひらや指先に今も痛みがあって、車のハンドルを握ることも、料理をすることもできずにいることなどを話してくれました。
今は、使える抗がん剤があと2種類だけになってしまったことなど、語られる内容はとても大変な状況なのに、それを以前と変わらぬおだやかな表情で、しかもときには笑みさえも浮かべて話す姿に、私はただおどろくばかりでした。
私は病もさることながら、現状に打ちのめされ、精神的に追いつめられていました。
私が自分の病状を話すと、彼女は、そんな病気があるのかと耳を傾け、私の苦しみに共感してくれました。
「今日はあなたに会えてうれしかった」
彼女と私、どちらの病のほうがどうと比べられるものではありませんが、少なくとも、手術をしたことや、現在の痛み、不自由さなどを考えると、彼女のほうが私より大変な思いをしているであろうことは想像がつきました。
ひと通り話し終えたあとで、私は彼女に、どうしてそんなにおだやかでいられるのかとたずねました。彼女は、「私もときどき落ち込むことはあるよ。でも、今日はこうしてあなたに会えてうれしかった。元気が出たわ。またね」とほほえんで、元気だったときと同じように、明るく手を振ってくれました。
同じく病んでいても、おだやかにほほえんでいる彼女と、ふさぎ込んで生気を失っている自分。この違いは何なんだろうかと、考え込まずにはいられませんでした。
10万人に一人という難病になったことに打ちのめされて、精神的にどん底にいた当時の私にとって、尊敬する彼女と10年ぶりに大学病院で再会したこと、そして彼女のふるまい、明るさ、笑顔に接したことは、人智を超える力のなせる業以外には考えられないと、鳥肌が立つ思いでした。
笑顔を絶やさなかった彼女
彼女はその後、4、5年の闘病生活を経て亡くなりました。最後の入院の日、見送りに来た近所の友人たちに、彼女は車の窓から笑顔で手を振っていたそうです。
一人暮らしだった家の中はきれいに片づけられていて、葬儀の手配や遺影の準備までされていたと聞きました。抗がん剤の副作用で物をさわることもできないほど痛む指先で、手で、彼女はそれらを行なっていたのかと思うと、私はただただ感じ入り、手を合わせることしかできませんでした。
彼女は逝ってしまったけれど、彼女が家族や周囲の人々に贈った笑顔は、今もすべての人たちの心の中にあり、とても大きな力を与えてくれているだろうと思います。
元気だったころはもちろんのこと、闘病中も、死を覚悟したであろうときでさえ、笑顔を絶やさなかった彼女。私にたくさんの笑顔をくれた彼女は逝き、私は今も病とともに生きています。そして私は、いまだに彼女のような笑顔になることはできていません。
ただ、あの大学病院で再会して以来、私の心の中には彼女がいます。その彼女に支えられて、私は前より少しは強くなったような気がしています。本当におこがましくてだれにも言えないけれど、私は彼女と一緒に生きている、そう思っています。