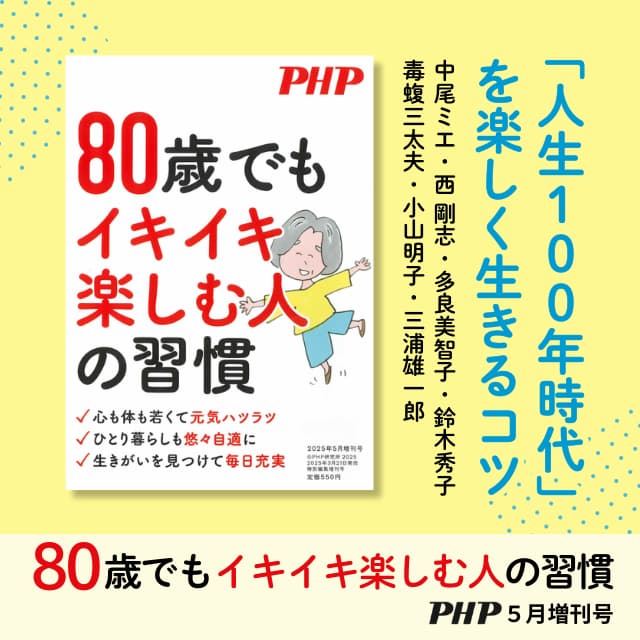第69回PHP賞受賞作
岡部晋一
神奈川県・元高校教諭・87歳
昭和20年8月15日、太平洋戦争が終わった。僕の家族8人は、昭和18年、空襲の激しくなった横浜から神奈川県海老名村に疎開していた。空襲で丸焼けになった横浜には、当分帰れなかった。
戦争は終わったけれど、食糧事情は悪化するばかりで、僕たち家族が疎開していた村には、秋になると食糧不足で飢えた都会の人たちが来て、大きな布袋を持ち、田んぼでイナゴを捕まえていた。イナゴを食料にして飢えをしのぐためだった。都会の人たちが農村で米を買うことは、法律によって禁止されていた。
僕は昭和20年4月に国民学校1年生になった。しかし、8月15日の終戦によって国民学校は小学校に変わり、登校のときに天皇陛下のご真影に敬礼することも廃止になった。1学期だけ使った教科書は廃止され、社会科の教科書は、配られた新聞紙大の紙を自分で切って束ね、母に糸で本の形にしてもらった。
小学校の6年間、僕たちはランドセルを背負った経験もなかった。友達の中には兄や姉が使用していた古びたランドセルを背負っている者もいたが、ごく少数だった。僕はランドセルを一度も背負わず小学校を卒業した。ランドセルの代わりに、母に縫ってもらった布袋に教科書や弁当を入れ、6年間通った。
また、僕は靴を一度もはくことなく小学校を卒業した。いつも村の老人が作っているわら草履をはいて通学した。体育の時間ははだしで運動場を走った。雨の日には家に傘が1本しかないため、学校を休んだ。
初めて味わった最高の味
僕が疎開していた村の小学校には、2つのグループがあった。疎開児童たちのグループはみすぼらしい服装で、毎日貧しい昼食を食べていた。いつも弁当箱にやせたさつまいもを3本。それさえ食べられない児童は、ポンプで汲み上げた小学校の井戸水を飲んで昼食にしていた。もう一つのグループは、銀シャリの弁当を食べている農家組だ。農家組の児童は疎開組の貧しさを笑い、疎開組の児童は農家組の田舎言葉を笑った。
秋の運動会のとき、担任の先生はクラス対抗のリレー選手に、疎開組であった僕と相沢を選んだ。相沢は陸軍少佐の父がフィリピンで戦死し、母親と2人で貧しい疎開生活を送っていた。そして農家組からは、KくんとYくんが選ばれた。先生は疎開組と農家組を仲直りさせたかったらしい。
運動会の昼、僕と相沢はさつまいもの昼食を食べようとしていた。そのとき、KくんとYくんがやって来て、「そんなもん食ってたら1組に負けちゃうべー、これ食えよ」と言って、大きな銀シャリのおにぎりを2つずつ僕たちの弁当箱に放り込み、さらにきゅうりの漬物と柿を弁当箱のふたに置いた。おにぎりには梅干しが入っていて、疎開生活で初めて味わった最高の食べ物だった。僕と相沢はKくんとYくんの思いやりに応えるようにメチャクチャに走り、1組に勝った。
あの日と同じように
その日以来、僕と相沢は2人と仲良くなり、農繁休暇のときには家に田植えや刈り入れの手伝いに行った。そのたびにおいしい真桑瓜やトマトをごちそうになった。僕たちが疎開先から都会に帰っても、KくんとYくんとの友情は続いた。
平成29年、農協の幹部として活躍していたKくんと、小学校の校長を退任したYくんが相次いで亡くなった。その翌年、僕と相沢は2人の墓参りに行った。Kくんの家に立ち寄ったとき、Kくんの夫人から、帰りに昼食を食べて行ってくださいと言われた。僕たちは小学校時代の運動会でのおにぎりの思い出話をし、おにぎりを食べさせてくださいと夫人にお願いした。
墓参りの帰り、Kくんの家の縁側で、あのときと同じ梅干しの入った大きなおにぎりをいただいた。相沢が「うめえなあ」とつぶやいた。顔を見ると、大粒の涙を流しながらおにぎりを食べている。僕も涙を流しながら白い大きなおにぎりを食べた。
あのときの思い出が心の底から湧いてきた。庭先を見ると、あの運動会の帰りに野道に咲いていたのと同じようなコスモスが咲いていた。僕と相沢はKくんとYくんに感謝しながら、世界一おいしい友情のおにぎりを思い出していた。