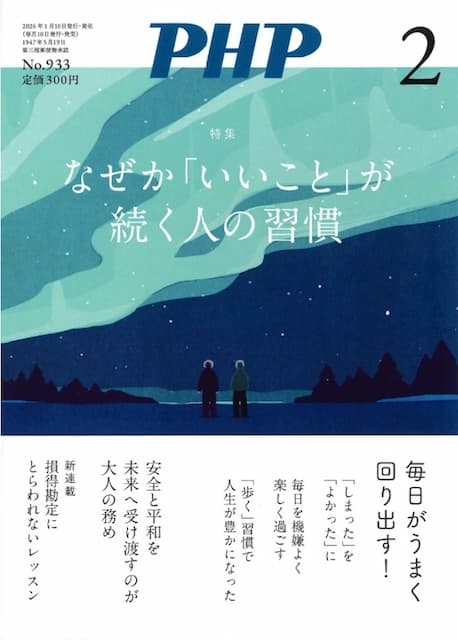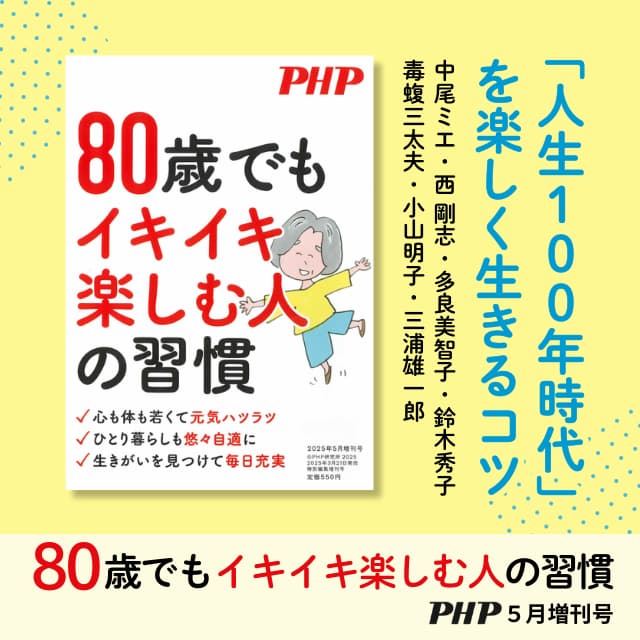第69回PHP賞受賞作
高島 緑
香川県・主婦・71歳
「衣も縫えるが肥やしもかつぐ」
小学5年生のとき、担任の松浦政夫先生に教わった詩の一節である。誰の何という詩なのかいろいろ調べてみたが、いまだにわからない。ただこの一節だけが、60年近くたった今でもはっきりと記憶に残っている。
古い木造校舎の教室。黒縁の丸い眼鏡をかけた先生が、詩をそらんじながら机のあいだをゆっくりと歩いていく。その光景を思い出すたびに、なつかしい母の姿が浮かんでくる。生涯、過酷な農作業と夜なべの縫い物に明け暮れた、まさにその詩のとおりの人生であった。
昭和27年、母は山深い奥伊予の封建的な農家に嫁いだ。私がこの詩を教わったころ、母は34、5歳であったと思うが、いつも顔を真っ黒にして、野良着に地下足袋姿で田畑の仕事や牛の世話に精を出していた。
どの仕事もきつかったと思うが、とりわけ裏山の急な段々畑に肥やしをかついで運ぶのは、子供の私が見てもずいぶん骨の折れる作業であった。体を斜めにしながら、ゆっくりと畑の中の細道を登ってゆく。足を踏み出すたびに、肩にくい込んだ天秤棒がしなり、両端につるした肥桶が揺れる。風呂焚きが子供の役目だったので、そんな日は母を喜ばそうと、いつもより早く五右衛門風呂を沸かしたものだ。
働き者の母は、昼間の仕事を終え夕食を済ませると、今度は夜なべに取りかかる。土間に敷いた筵の上で俵を編む父とぽつりぽつりと言葉を交わしながら、茶の間で縫い物をする。
何でも縫ってくれた母
「ねえさんよ、縫うてくれんか」。母のもとには、近所の人たちがよく着物の仕立てを頼みにきた。縫い物など習った話は聞いたこともないのに、母は板の間に反物を広げ、薄暗い裸電球の下、慣れた手つきで布を縫ってゆく。それが不思議で、「どこで習うたん?」と聞くと、「なんちゃ習いはせんけんど、昔はみんな自分で覚えて縫いよったんよ」と笑いながら母が答える。
手先が器用な母は何でも上手に縫ったが、自分は素人だからと、仕立て代をわずかしか受け取らなかったため、だんだん遠くの人からも依頼がくるようになった。やがて日本舞踊の衣装まで頼まれるようになり、母の夜なべは忙しくなった。夜なべは、母が体調を崩して針が持てなくなる85歳のころまで続いた。
貧しかったわが家では、子供のころ私たちきょうだいの着る物は、ほとんど母が縫ってくれた。小学校の修学旅行のときには、自分の青い着物をほどいて、私のジャンパースカートに仕立て直し、ブラウスは薄桃色の花模様。近所の小間物屋で買ってきた安い端切れをつなぎ合わせて縫ってくれた。
高校に上がると、制服代を倹約して、借りてきた友達の制服を手本にブラウスまで縫った。白いブロード生地は少し硬くて、みんなの制服とはどことはなしに違っていたが、私は3年間、それを着て通学した。
タンスと針箱の中の宝物
高校を卒業すると、私はすぐに都会に出た。夜学に通ったあと、夜勤のある仕事に就いた私には、年頃になっても着物を着る機会などまったくなかった。それなのに母は、これから不自由しないようにと、娘の着物の心配をし始めた。
たびたび送られてくる手紙には、今、どういう柄のどういう物を縫っているのか、毎回それはくわしく書かれていたが、仕事に追われて忙しい私には、申し訳ないことにそれらに関心を寄せる余裕はなかった。そればかりか、帰省するたびに仕立て上がった物を広げて見せたがる母に「着物はいらんけん」、そんなそっけない言葉を投げかけた。
当時母は、農閑期には、家の近くで行なわれていた国道工事の現場で日雇いの仕事をしていた。男衆に交じって泥まみれになって働き、日銭を貯めては生地を買い、夜なべで私の着物を縫った。訪問着や付け下げ、小紋に喪服。ささやかな稼ぎが着物代に消えてゆく。母に無理をさせたくない気持ちが、ついそんな尖った言葉になってしまう。それでも母は黙って縫い続けた。
結局、ほとんど袖を通さずじまいだが、それらは今、わが家のタンスの中に全部大切にしまってある。
私の針箱は、母を送ったときに形見にもらってきたたくさんの使いかけの糸であふれている。これらの糸を使った夜なべのひと針ひと針には、母の祈りが込められている。
もうすぐ7回忌 。節くれだったあの母の指先に、心からありがとうを言いたい。