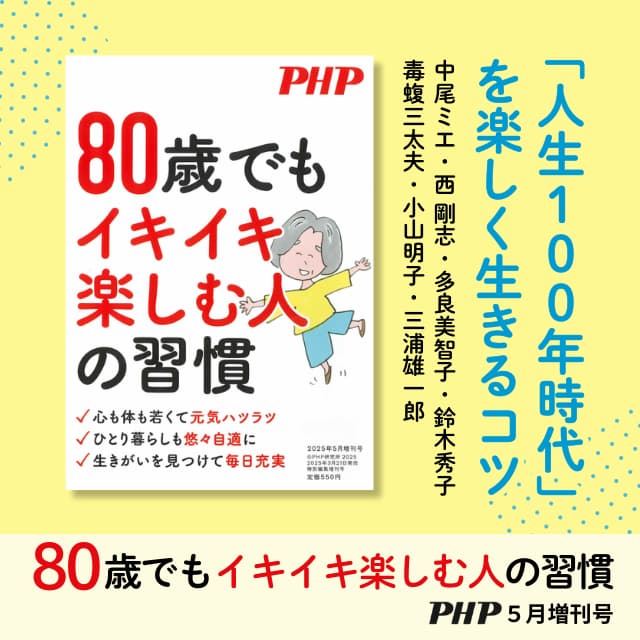第69回PHP賞受賞作
石川和巳
埼玉県・無職・68歳
若いころから、走るのが好きだった。陸上競技をやっていたわけではない。趣味のジョギングだ。それでも20代、30代のころは、地元の市民大会などにも挑戦した。小学校の教員をしていたので、子供たちともよく一緒に走った。運動することの楽しさ、体を動かすことの心地よさを、子供たちにも伝えたいと思っていた。私の体もよく動いた。
ところが40歳を過ぎて教頭になると、状況が一変した。段違いに忙しくなり、ジョギングをするような余裕がまるでなくなった。出勤は早く、帰宅は遅い。休日出勤は当たり前。気もつかう。体の疲れよりも、心の疲労が大きく、つぶれそうになった。
そこで、運動不足とストレス解消のため、もう一度走ってみようと思い立った。多少疲れていても、時間がなくても、少しずつ走ればよい。短い時間でも、のんびり各駅停車に乗ったような時間を楽しみたいと思った。
ある朝、まだ暗いうちから走り始め、ゴール近くでちょうど真正面に日の出を見るような形になったことがあった。そのとき、地球が回るのと一緒に、私自身も生きて躍動していることを実感し、体が震えた。ジョギングを始めてよかったと思う瞬間だった。
走るとき、私はいつも一人だった。そのほうが、自分自身をしっかり見つめることができる。一人きりのジョギングは、自分を取り戻すための、特別な時間となっていった。
私には、もう一つ趣味があった。川柳だ。我流で新聞の川柳欄に投稿し、たまに掲載されるのを楽しんでいた。しかし、仕事の忙しさで川柳をつくる余裕はなくなり、いつの間にか投稿もやめてしまった。
ジョギングと川柳
ところがジョギングを再開してみると、思いがけない変化があった。頭がすっきりするからだろうか、走りながら周りの景色がよく見える。道端に咲いた小さな花や、夜明けの空を横切っていく鳥の群れ。ふだん見えていても見てはいなかったものがたくさんある。
いつの間にか、そうした新しい発見を、走りながら五七五のリズムに乗せて口ずさむようになった。気のきいたフレーズが浮かぶと、頭の中からこぼれ落ちないようにして、家に帰るとすぐにノートに書き写した。それを川柳として仕上げて、また新聞に投稿を始めた。そんな私のジョギングの時間を、家族はよく理解して、とても大切にしてくれた。
ところが、少し困ったことがあった。走っている最中に、一つ気のきいた言葉が浮かぶと、代わりにそれまで頭の中にメモしていたものが、スーッと消えてしまうのだ。どうやら私の頭のキャパシティーは、せいぜい5つほどのフレーズが限度のようだ。忘れないようにぶつぶつ言いながら走っている姿を想像すると、自分でもおかしかった。
しかしそれが、やがて笑いごとではすまなくなったのだ。私の脳の機能に、トラブルが発生した。
妻と一緒の散歩の時間
私は校長になっていた。定年退職まであと数年というころ、子供たちと校庭で縄跳びをしていたときだった。なぜか体全体が重く感じられ、上手に跳べない。そんなはずはないと思いながらも、同じようなことがいろいろな場面で続いた。勧められて、病院へ行った。
パーキンソン病だった。死ぬまで治らないという難病だ。こんなとき、以前だったら、ジョギングで汗を流して、身も心もリフレッシュしたものだ。だがもう、手や足が言うことを聞いてくれない。
しかし逃げたくはなかった。できることはまだたくさんあるはずだ。走ることはできなくても、歩くことはできる。簡単なことだ。走る代わりに、歩けばよい。
最初は、ジョギングと同じコースを歩き切ることを目標とした。しかし病気は確実に進行し、だんだん距離も時間も短くなり、まるでリハビリの歩行訓練のようになってしまった。でも、ゆっくり歩けば歩くほど、さらに見えないものが見えるようになった。ポケットにはメモ帳が入っている。いくつ言葉を見つけても、もう忘れる心配はない。
やがて杖が必要となった。杖に頼りゆっくりゆっくり歩く。一日一日を懸命に生きる中で、この散歩の時間が私の体と心を癒やしてくれた。そして私は、勇気と自信を取り戻し、何とか定年退職までたどり着くことができた。
発症から10年以上。病状がさらに進んだ今、散歩も妻と一緒だ。一人ではどこへも行けない。しかし妻がいる。二人で歩く楽しさを知り、新しい幸せの形を見つけた。だから、妻と一緒に歩く時間が、今一番あたたかい。
「妻の手がそっと重なる影法師し 」。川柳にも、妻の句が増えてきた。