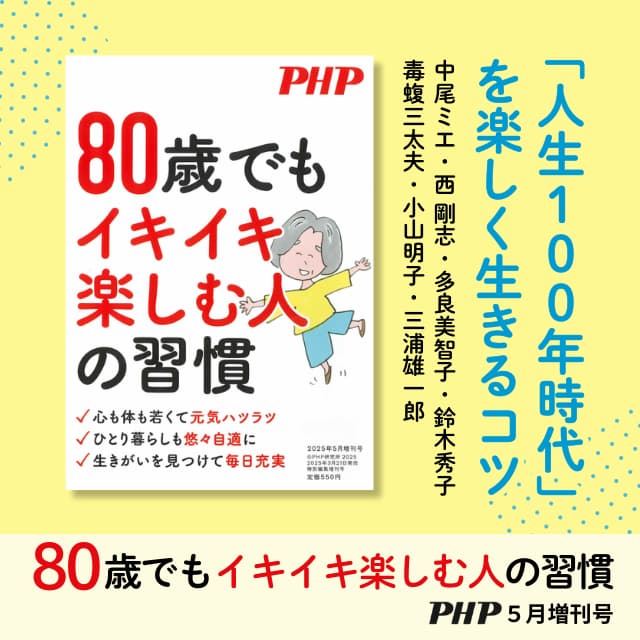第57回PHP賞受賞作
小松﨑潤
東京都清瀬市・会社員・35歳
僕はできが悪い。昔から勉強もスポーツも全然できなかった。成績は下から数えたほうが早いし、高校の野球部では万年補欠だった。
練習ではいつも球拾いをしていた。グラウンドに散らばった球を何も言わずに拾う。球を拾った数だけ、補欠の辛さを実感した。
それでも高校3年間、試合を見に来てくれた人がいた。僕の爺ちゃんだ。
試合に出られなければ、ベンチにも入れない。補欠選手の僕の居場所は、スタンドの観客席だった。爺ちゃんは毎回僕の隣の席に座ってきて、いつも2人で試合を見ていた。
仲間のバットからひびく快音も、ホームベースで見せるハイタッチも、すべてが羨ましかった。
僕だって試合に出たい。思いきりバットを振りたい。どんどん悔しさがこみ上げてきて、拳を握りしめながら試合を見ていた。
そんな手を爺ちゃんは上から握った。僕らに会話はなかった。
あのとき、部活をやめて、野球を諦めることは簡単だった。でも、できなかった。僕の手を握る爺ちゃんの手が、握る強さが、「やめるなよ」と言っているように感じていた。
「おまえは手を出すな」
高校3年の夏、僕は部活を引退した。それと同時に爺ちゃんは脳梗塞で倒れた。
幸い一命は取り留めたが、介護は避けられなかった。爺ちゃんは歩くことも食べることも困難になった。
家族の中で男は僕一人だったので、はじめは僕が爺ちゃんを風呂に入れていた。
しかし、あるとき僕は爺ちゃんの大きな身体を支えきれずに転倒させてしまった。あわや救急車という事態に母は怒り、早々に介護ヘルパーをお願いすることになった。
「おまえは手を出すな」
その言葉がこれまで浴びたどんな叱咤よりも心に突き刺さった。
それからというもの、日中になると介護ヘルパーさんが爺ちゃんを風呂に入れた。女性ふたりでも爺ちゃんの身体は重く、正直手に負えないように見えた。
あんなに大変そうなのに、僕は見ているだけで何の役にも立たない。バッターボックスに入りたいのに、スタンドで見ていることしかできなかった、あの頃と同じ悔しさを味わっていた。
爺ちゃんは日に日に認知症が進み、風呂を嫌がるようになった。服を脱がせようとするヘルパーさんを叩き、時には大きな声をあげた。
とてもじゃないけれど見ていられなかった。あんなに嫌がって、興奮している爺ちゃんを見ているのが辛かった。そこには昔の穏やかな優しさはなかった。
そんなとき「ちょっといいですか」とヘルパーさんが僕を呼んだ。何かと思えば、これから風呂に入れるので、その間、爺ちゃんの手を握っていて欲しいという。
僕は言われるがまま、爺ちゃんの手をとった。
握った爺ちゃんの手はゴツゴツしているけれど、カイロのように温かかった。それはスタンドで補欠の僕を慰めてくれていた、あの頃の手のままだった。
僕が手を握ると、さっきまで暴れていたのが嘘のようにおさまった。手を握ったまま、爺ちゃんは風呂の中に身体をゆっくり沈めた。
すると、どこかホッとした表情になった。
僕の手にもできることがある
その顔を見ながら、僕は部活の後輩のことを思い出していた。
その後輩も僕と同じく、いつも補欠だった。
もう部活をやめたい、と相談されていた。
僕にはかける言葉がなかった。だから何も言わずに後輩の背中をさすった。時にはバカをやって笑わせた。
僕の引退の日、その後輩から「先輩のおかげで部活を続けられました」と言われた。はじめて、野球をやっていてよかったと思った。
この手が誰かを幸せにしたのだと、いとおしく感じた。
爺ちゃんにふれる手元を見つめ、後輩の言葉を思い出した僕は「僕の手にもできることがある」と思った。
爺ちゃんの安心した表情がそう気づかせてくれた。
「日陰にしか咲かない花もある。でも、その花にしかできない役割だってある」
そう爺ちゃんは教えてくれた気がする。
後輩の背中をさすった手、爺ちゃんの手を握った手。どれもできの悪い僕の手。
だけど、爺ちゃんのほほえみも、後輩の言葉もどれも僕の宝物だ。だから今、僕は前よりしっかり前を向いている。
できの悪い僕だけど、できることがある。
この手があり、この手が温かいかぎり、僕は何かできると信じている。