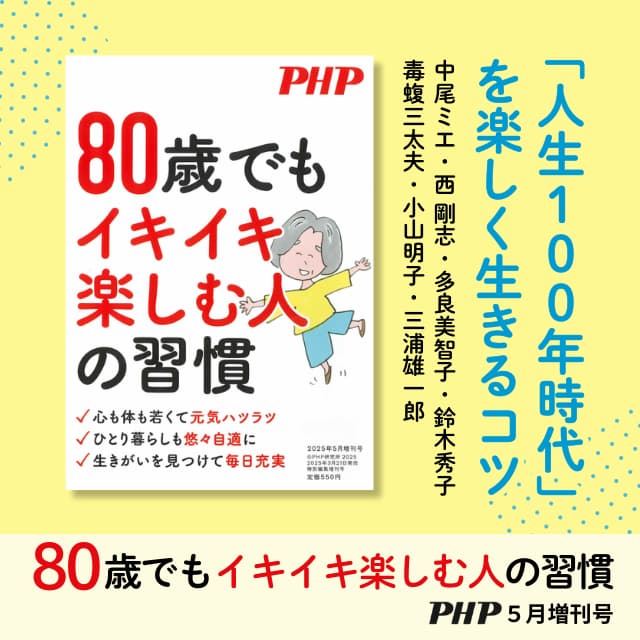第58回PHP賞受賞作
坂上莉奈
東京都国分寺市・接客業・三十二歳
夢を見た。
私は白いドアの前に立っている。
ドアを開けると、真っ白な部屋が現れた。
小さなヤシの木やソテツが床からたくさん生えている。
そして真っ白な大きなソファーに、七年前に亡くなった祖父が腰かけていた。
「私、お迎えが来ちゃった?」
そうたずねると祖父は鼻息を荒らげ、大きな声で笑った。特徴のある笑い声、大きな口。
「デカは死んでいない!」
デカというのは私のことである。祖父は孫が八人いたにもかかわらず、全員「デカ」と呼んでいた。天然な人だった。
「じいちゃんはデカを応援しているぞ!」
「ありがとう。いろいろあったけれど、マイペースに楽しく生きているよ」
「それでいいんだ。デカの人生はデカのものだ! じいちゃんはいつでも見守っているからな!」
あ、この言葉、懐かしい。
そう思った瞬間に、また祖父は大声で笑い、私は目が覚めた。
夢から覚めて思いだしたのは、幼い頃のことだった。
「星になったなんてきれいごとだ」
私は、四歳になる春に父を亡くした。
幼いながらに父との別れが悲しくて、毎日涙が止まらなかった。泣いては持病の喘息をこじらせ、高熱を出した。しばらくすると、ストレスで髪も抜け始めた。
母は姉と私を抱え、家計を支えることに一生懸命だった。仕事が忙しく、私につきっきりではいられなかった。
悲しみは癒えず、母に頼ることもできない。私の円形脱毛症は進んでいき、ついにしゃべることもできなくなった。
祖父がやってきたのはそんなときだった。車で二時間ほどかかる場所に暮らしていたが、母の代わりに私の保育園の送り迎えをしてくれることになった。
祖父は、お迎えのころになると、いつも一番に現れた。開門時間より三十分も早く来てしまうため、しょっちゅう先生たちを困らせた。一方、保育園の子どもたちからは大人気で、その外見と荒い鼻息から“ゴリラじいちゃん”と呼ばれた。
父が亡くなり、髪が抜けるようになってから、私は保育園で「かわいそうな子」として扱われていた。同情されるのが嫌だと感じていても、声は出ず、何も言えなかった。
ある日、退園する際に、先生から、
「元気出してね。りなちゃんのお父さんは、お星さまになって見守ってくれているからね」
と声をかけられた。すると、祖父は、
「いやぁ、先生、それはだめだ。星になったなんてきれいごとだ。デカは父親の死に向き合っているんです」
と言った。祖父は、子ども扱いすることが大嫌いで、私にはそれがありがたかった。
その翌日、「今日は保育園を休もう」と祖父が言って聞かなかったので、保育園を休み、祖母が握ってくれたおにぎりをもって、二人で公園まで歩いた。
公園の近くを電車が通り過ぎるたびに、祖父は大きく手を振った。「じいちゃんな、昔は駅長さんをやっていたんだ」。私が話せない分、祖父はたくさん話しかけてくれた。
暗闇から連れ出してくれた祖父
公園に着くと、祖父は大きなおにぎり二つを一瞬でたいらげてしまった。私が自分の分のおにぎりを差し出すと、「遠慮することはねぇんだ」と言った。真っ黒な強い瞳で私を見つめ、肩をつかんだ。
「いいか。ゆっくりでいいから、デカの思うように生きるんだ。じいちゃんはいつも見守っているからな」
そう言って、私を強く抱きしめてくれた。
その腕があたたかくて、でも背骨が折れてしまうんじゃないかというほど強くて、「いたい」
と私は声をあげた。
久しぶりに私が話したことに祖父はびっくりして、手を放し、立ち上がった。声をあげて喜び、泣いていた。
「デカ! よくやった!」
祖父はまた強く私を抱きしめると、いきなりブーッと大きなおならをした。それがおかしくて、私はケラケラと笑った。祖父の涙を見たのは、そのときが最初で最後だ。その後、母が一カ月間、仕事を休んでくれた。家族と一緒に過ごすうちに、薬を塗っても生えてこなかった私の髪の毛は元に戻った。
あの頃、隣に祖父がいてくれなかったら、私はずっと暗闇の中にいたかもしれない。心の中にいる祖父は強くて、あたたかくて、今も私に勇気をくれる。