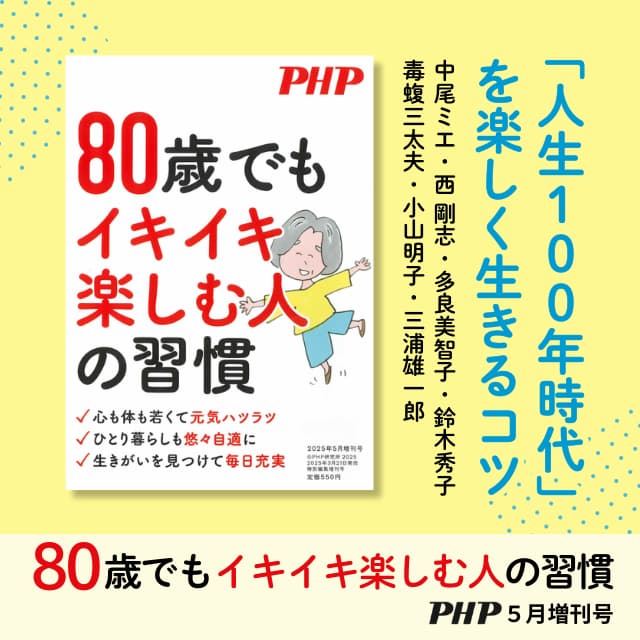第63回PHP賞受賞作
菊地真由美
北海道札幌市・主婦・
58歳
私が小学生のとき、父が脱サラして書店を始めた。私はその店が大好きだった。子供のころはお店屋さんごっこの気分で店に立ち、中学や高校の帰りには立ち寄り、大学生になるとバイト代をもらって手伝った。
父が亡くなってからは一人で店を経営していた母だが、高齢になると続けることが厳しくなった。母の代で店を閉めることになると思っていたが、私は継ぐことを決意した。40歳のときだった。
子供のころから慣れ親しんだ書店の仕事は、私に合っていた。書店は居心地のいい場所で、仕事を趣味のように楽しんだ。この仕事を長く続けたい、高齢になってものんびり続けていきたい。そう思っていた。
50歳を過ぎて目に病気が見つかった。失明する可能性のある病気だった。仕事は続けられると思っていたが、視野の悪化を実感するようになり、書店の将来を考え始めた。
書店の仕事は店頭に立つだけでなく、発注や管理、経理などの仕事もある。視力が悪くなれば、お客さまやお取引先に迷惑をかけることも出てくるだろう。閉店を考えざるを得なかったが、なかなか決断できなかった。大切な店を失いたくなかった。あきらめの悪い私は、今年こそ閉店すると毎年母に話しては延期した。
閉店を告知することで気持ちにケリをつけることにした。しかし、閉店の案内を書くときになると、「心残りで」「まだ続けたいが」などの心情が文にあふれ出てしまい、夫には事務的に書くべきだと指摘される始末だった。
うれしくて、ありがたくて
告知をしてからも未練を断ち切れず、「まだ閉店を取りやめられる」と毎日考えていた。結局、その覚悟ができないまま、あっというまに私の店は閉店した。不思議とさびしさはなく、ただ、もう撤回できないのだなと思った。55歳の秋の日だった。
翌日から片づけが始まった。シャッターを下ろした店で、返品するために本を箱詰めしたり、こまごまとした物を処分したり。さびしさを感じないよう、閉店を意識しないよう、黙々と作業をしていたのだが、思いもよらないことに気持ちを逆なでされた。
シャッターに貼ってある閉店の案内を読んだ人の声だった。案内には閉店することとお礼を書いていただけで、閉店の理由は書いていなかった。それを読んだ人が「ついに潰ぶれたね」「潰れちゃった」と言うのだ。
苦悩の末に閉店したというのに、経営が続かずに潰れたと言われることは、「両親の期待を裏切った、失敗した」と烙印を押されているようでやりきれなかった。片づけが進み、スペースが広くなるたび、現実が重くのしかかった。その重みに追い打ちをかけるように、シャッターの向こうから聞こえる「潰れた」という遠慮のない言葉が、私を傷つけた。
その日も、シャッターの向こうで貼り紙を読む人の気配がした。若い女性二人のようだ。またかと耳をふさぎたくなった。
一人が言った。「ついにやめちゃったんだね。残念だね」。もう一人が言った。「いいよ、いいよ、もういいよ。42年もがんばったんだって。充分にがんばったよ」と。さらに二人は「お疲れさまでした」と言ってくれた。
私は思わず立ち上がり、そっとシャッターに近づいた。向こうで女性たちが頭を下げている気配を感じた。出て行きたい気持ちをおさえ、見えない女性たちに深く頭を下げた。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、と。
うれしくて、ありがたくて、胸がいっぱいだった。「もういいよ」「充分がんばった」「お疲れさま」。彼女たちの言葉が何度も何度もこだました。「よくがんばったな」と、父が閉店をゆるしてくれたように感じた。
シャッターの向こうには
店を継いでからというもの、亡き父に「店をたのんだぞ」「しっかりやってくれよ」と言われている気がしてならなかった。期待に応えようとがんばってきた。閉店は父を裏切ることに思えて苦しかった。
彼女たちのおかげで、「もういいよ」と父にゆるされたように思え、肩の荷を下ろすことができた。店を守らなければならないという使命から解放された私は、これでよかったと閉店を受け入れることができた。
潰れたと言われて傷ついた心も、未練を断ち切れない鬱々とした気持ちも、もっとできたのにというあきらめの悪さも、「充分だ」と父がなぐさめてくれた。私は安堵し、ようやく父の墓前に報告ができた。
今おだやかな気持ちでいられるのは、あの言葉があったから。心から感謝していることを、彼女たちは知るよしもないだろう。
ふと思うことがある。シャッターの向こうにいたのは父だったのかな、と。