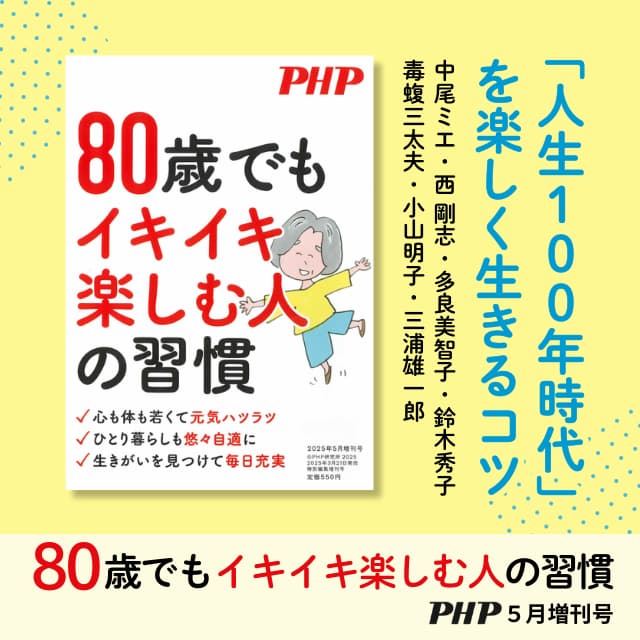第63回PHP賞受賞作
吉田恵子
愛媛県松山市・自営業・75歳
高校卒業間近のある日のこと。昨夜から降っていた雪は、朝になると30センチほど積もっていた。ひと冬に何度か雪が積もることはあったが、3月の雪はめずらしい。
私は4年前から牛乳配達のアルバイトをしていた。ふだんは自転車で配達するが、雪が積もったり、道が凍っていたりすると歩いての配達となる。今朝は4時半に起きた。牛乳は隣町の久万町から来る。そこは小田町よりも標高が高いのでもっと寒い。
4度目の冬となると、雪の日の身支度もさまになる。長靴に雪が入らないようにと、ナイロンの風呂敷を脚絆の代わりに巻き付ける。しばらく待つとガチャガチャと牛乳瓶のかち合う音とともにトラックがやってきた。
「おはよう、やれやれ、遅うなってしもうた。すまんかったなあ。だいぶ待ったろう」
「それより真弓峠のほうはどんな具合ですか、大変じゃったでしょう」
「だいぶ積んどるよ。40センチはあるな。そう思うて、今朝はいつもより早う出てきたんじゃけど、倍以上もかかってしもうた」
幌の雪を払いながら50本の牛乳を出し、ホッとしたような声で話す。
「何かあってもいけん思うてな、今日は息子を連れて来たんよ」
助手席では、私とあまり年恰好の違わない男の子が、黙って二人の話を聞いていた。
「危ないけん、滑らんように、気いつけて帰ってくださいね」
そう言って私が手を振ると、助手席の息子も、はにかんだ笑顔で小さく手を振った。
二つの袋に牛乳を15本ずつ詰めて、両手に提げる。20本はあとから配るので残しておいた。30本の牛乳は、両手に分けてもさすがに重い。雪道を歩くとなおさらである。
僕が半分持っちゃるけん
そのころの牛乳はぜいたく品で、だれでも飲めるものではなかった。体の弱いお年寄りや病気の子供など、飲む人は決まっていた。牛乳を配る手はかじかんでいて、手袋の上から何度も息を吹きかけ、手をこすり合わせた。
「姉ちゃん、手伝いに来たよ」
声がして振り向いた。残りの20本の牛乳を自転車に積んで押す弟と、倒れないように支えて歩く妹がいた。
「あんたら来てくれたん」
寒さの中で孤独と闘っていた私は、うれしさを隠せなかった。妹は小学6年生、弟は中学3年生。来てくれるとは思っていなかった。
「歩いて配るんは大変じゃろう思うて、手伝いに来たんよ」
「僕が半分持っちゃるけん」
そう言うと、弟は袋を一つ、自転車のハンドルにかけた。3人いれば自転車も簡単に動かせる。頼もしい助っ人だ。
最後の一本になったときだった。妹が、
「あそこはうちが行くけん」
そう言って雪の中を走って行った。玄関先に黄色い牛乳箱がある。ふたを開けて、空瓶を取り出し、新しい牛乳瓶を入れる。
そのとき、鈍い音がした。足元に白く牛乳が飛び散り、積もった雪の中に吸い込まれていった。箱の中に入れ損ねたのだ。妹は今にも泣き出しそうな顔で突っ立っていた。
早うお行き
「大丈夫? ケガせなんだかぁ」
呆然と立ちすくむ妹に声をかけた。余分な牛乳がないのと寒さとで、どうしたらいいかわからず、ほんの一瞬、妹を責めかけた。が、すぐに打ち消した。寒い中、朝早くから手伝いに来てくれたのだ。怒るわけにはいかない。
「手ぇ切ったらいけんけん、いろわれんよ。うちがするけん」
そう言って割れた牛乳瓶を片づけようとしたとき、玄関の戸が開いた。
「危ないけん、そのままにしとうきや。おいさんが片づけとくけんな。あんたら寒いのに偉いなあ。ケガせんかったかな。今日の牛乳代はおいさんとこに付けといてええけんな」
「すんません、代わりの牛乳がないんです」
「ええよええよ。あんたも大変なんじゃけん、心配せんでもええんよ」
「ほんとにすんません」
「あんたらは、ほんとに仲がええなあ。学校があるんじゃろ、早うお帰り」
「ええんですか、牛乳がのうても」
「かまんかまん、1日ぐらい、のうてもええよ。早うお行き。がんばりいよ」
「ありがとうございます。本当にすんませんでした」
それは60年前の田舎町の朝の出来事だった。牛乳が10円、配達賃は2円の時代で、家計を助けるために始めた牛乳配達だった。
人の優しさに出会い、思いやりの心を教わった。小田川沿いの小さな町で育った少女時代。あのときの小父さんの言葉は、忘れられない思い出として、今も心に残っている。