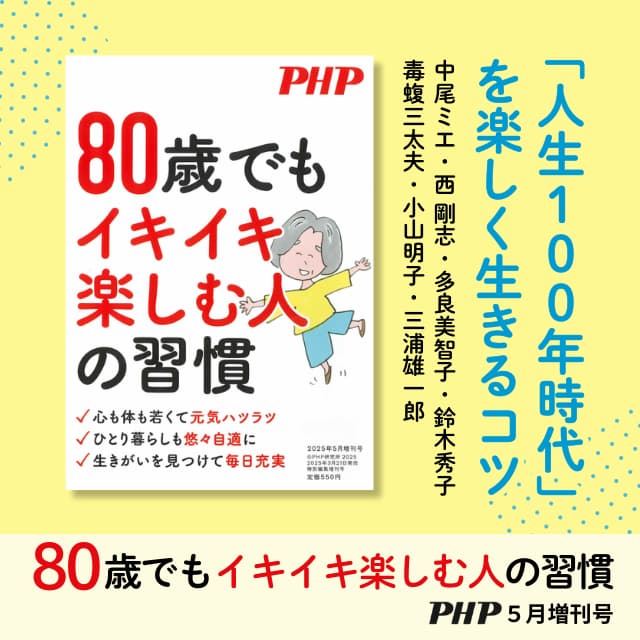第68回PHP賞受賞作
宮澤由季
埼玉県・自営業・38歳
お盆休みにひどい風邪を引いた。アパートで一人高熱にうなされていると、あの名前が口をついて出た。「たすけて、おかゆマン」。
最後にこの名を口にしたのはいつだろうか。母の葬儀を終えた晩、疲労から寝込んでしまったとき以来かもしれない。「おかゆマン、早くきて」。乾いた口内にじんわりと唾液が滲んだ。なつかしい感覚に熱っぽい頬がゆるむ。同時に母のふくよかな背中が目に浮かんだ。
私の実家では、体調を崩したときの食事に愛称をつけていた。すりおろしリンゴは、スリリン。生姜スープは、ほかほか丸。そしておかゆは、おかゆマン。幼少期の私はとても体が弱く、幼稚園で発熱しては、頻繁に母に迎えにきてもらっていた。そんなとき、母は決まってこんな寸劇を始めた。
「ユキちゃん、おかゆマンの出動許可をお願いします」。自転車のうしろで揺られながら、私は熱っぽい顔を上げて答える。「おかゆマン、しゅつどう」。すると母は拳を無線機のように口元に当てた。「こちら母。聞こえますか、どうぞ」。わざと声をこもらせる。「ヒーロー派遣センターにおかゆマンの出動を要請します!」そして無線機を口から離すと、今度は声色を変えて、「了解、どうぞ」と言った。
それを合図に自転車が加速する。私は母の満月みたいな背中にしがみついた。「お母さん、おかゆマンきてくれる?」「もちろん! さぁ早く帰って準備よ!」そうやって私たちは家路を急いだ。
母特製の「へんしんアイテム」
おかゆマンは必ず土鍋でやってきた。昆布だしで時間をかけて炊いたとろとろの5分がゆだ。「おかゆマン、ただいま参上!」母の声と同時に食卓に土鍋が置かれる。私は身を乗り出して拍手で迎えた。「待ってました、おかゆマン!」ゆっくりと土鍋のふたが開かれる。湯気で目の前が白くなる。熱がまつ毛に触れ、お米の甘い香りが顔をなでる。湯気が晴れると、おかゆマンの輝く姿がはっきりと見えた。つやつやのおかゆは、まるで真珠をしきつめたよう。おなかがグウと鳴った。
私は母のエプロンをくいっと引く。「お母さん、へんしんアイテムは?」母はニヤッと笑って、小鉢がたくさん載ったおぼんを運んできた。きざんだ生姜、みょうが味噌、大根の葉の漬物、蜂蜜漬けの梅干し、やわらかく茹でた星型の人参。どれも母特製の薬味だ。
待ちきれずに手を伸ばすと、母が首を横に振ってウインクした。「これは後半のお楽しみ」。私は「はいっ」と素直に返事をし、普段より行儀よく手を合わせた。「いただきます!」母はクスクスと笑いながらおかゆをすくい、丁寧に冷まして私の口へ運んだ。
「おかゆマン、おいしい!」お米の甘みが口いっぱいに広がった。やさしい熱が喉へ流れていく。次を急かすように母と土鍋を交互に見た。私が笑うたび、母もうれしそうに目を細めていた。
ヒーローの正体
やがて土鍋の半分を食べ切ると、母が「そろそろね」と私に耳打ちした。待ちに待った変身タイムである。私は興奮気味に小鉢をのぞき込んだ。味だけでなく色合いも考えて選ぶ。きざんだ生姜をひとつまみ、大根の葉の漬物を少々。最後に星型の人参を2枚載せた。真っ白だった茶碗の中が一気に華やぐ。私は腰に手を当て、大きく胸を反らすと、「おかゆマン! へーんしん!」と声を張った。
すかさず母がれんげを渡してくる。今度は自らおかゆを口に運んだ。お米の甘さと薬味のしょっぱさが口の中で混ざり合う。生姜の香りが鼻に抜ける。甘酢っぱい梅干しが唾液を誘い、砕けた星型の人参がつるんと喉を通った。私は夢中で食べた。顔から汗が吹き出す。腹の底から力がみなぎるようだった。
そして茶碗の底が見え始めると、母が私の肩を叩いた。「準備はいい?」その右手には醤油瓶が握られている。私は額の汗を拭い、力強くうなずいた。それから茶碗に手を添え、元気よくこう叫んだ。「おかゆマン! へーんしん!」醤油が1滴垂らされた。すばやくかき混ぜると、あっという間に茶碗の中の色が変わった。私たちは声をそろえて言った。「ゴールドおかゆマンが病気を成敗!」黄金色のおかゆを、ひと粒残さず食べた。
私はアパートの狭いキッチンに立った。一人用の土鍋を戸棚から引っ張り出し、米と水を用意する。そして手で無線機の形を作った。「こちら娘。聞こえますか、どうぞ」。自分でもおどろくほど、声が母にそっくりだった。「ヒーロー派遣センターにおかゆマンの出動を要請します」。あのころから気づいていた。本当のヒーローは薬味作りが上手で、満月みたいな背中をしていると。耳元で、「了解、どうぞ」と聞こえた気がした。